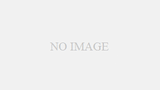令和7年9月に開催される定例会関係の投稿です。
- 1)企画振興事務事業18節「地域間幹線系統確保維持事務補助金」
- 2)移住促進事務事業11節「移住プロモーション動画及び動画撮影(春・夏)」
- 3)住環境整備事務事業7節「子育て世帯住宅取得応援奨励金」
- 4)ふるさと寄附促進事務事業7節「報償費」
- 5)賦課徴収事務事業18節「相続登記支援補助金」
- 6)老人福祉事務事業7節「介護人材就労支援金」
- 7)子育て支援事務事業19節「ファミリーサポートセンター事業」
- 8)健康教育相談訪問事業13節「子育て支援サービスアプリの使用料」
- 9)農地利用促進事務事業
- 10)林業推進事務事業12節 森林教育委託料
- 11)産業活性化補助金について追加質疑
- 12)中小企業融資事務事業18節
- 13)中学校運営管理事業17節
- 14)郷土資料保存事務事業
- 15)ブドウ・ブドウ酒事業の損益計算書
- 16)ブドウ・ブドウ酒事業会計のキャッシュフロー計算書
- 17)ブドウ・ブドウ酒事業会計の棚卸資産残高
一般質問
小中学校修学旅行費用の補助金増額について
片山 全国的に物価上昇が続く中で、実質賃金は減少傾向にあり、家計の負担感が増しています。義務教育の一環である修学旅行費用は、原則として保護者負担となっていますが、実質的には避けがたい「義務的支出」と言えます。池田町では今年度から、小学生1万円・中学生2万円の補助制度が導入され、保護者からは「助かる」との声が寄せられています。ただ、「もう少し支援額を増やしてほしい」との意見もあります。
町の財政状況を踏まえると全額補助は難しいかもしれませんが、少なくとも50%程度を町が負担する形が適当ではないかと考えます。この点について、教育長のお考えを伺います。
教育長 修学旅行など教育活動に関する費用のうち、宿泊費や交通費のように児童生徒に直接利益があるものについては、一般的に「受益者負担」とされています。そのため、一定の保護者負担をお願いしているのが現状です。しかし、すべての保護者が安心して子どもを就学させられるよう、過度の負担を避ける支援策を講じることも重要です。令和6年度には、教材費・部活動・少年団・体験活動・災害給付掛金など、約2,000万円(児童1人7.4万円、生徒1人4.8万円)の支援を行っています。また、学校給食費については物価高騰による値上げ分(約470万円)を保護者に転嫁せず、据え置いています。さらに今年度からは修学旅行費補助金として約100万円を支援しています。今後については、限られた財源の中で、物価対策・子育て支援・保護者負担軽減を総合的に検討しながら判断していきたいと考えています。
片山 修学旅行費補助は、所得制限のある支援とは異なり、すべての子どもに公平に効果が及ぶ施策です。教育の平等の観点からも、非常に意義のある支援だと考えます。税金の使い道としても、できるだけ多くの子どもたちに届く公平性の高い施策に優先的に充てるべきです。物価高騰対策にとどまらず、町の「子育て支援策」としても大きな意味を持つと思います。したがって、この修学旅行費補助は、可能な限り手厚くすべきだと考えますが、教育長の見解をもう一度伺います。
教育長 保護者負担の軽減や子育て支援は教育現場でも非常に重要な課題だと認識しています。そのため、修学旅行に限らず幅広い経費について、必要な予算措置を講じてきました。今後も、経済対策・物価対策・子育て支援・保護者負担軽減など、相互に関わる分野を総合的に見ながら、全体のバランスの中で判断していくことが必要と考えています。
出産祝い金・育児支援金廃止に代わる直接的支援制度の創設について
片山 今年度池田町において出産祝い金や育児支援金が削減されたことについて、町の方々からは残念であるという声があります。特に令和7年6月24日に町のウエブサイト声の広場に投稿された意見の中には、育児を行う中でただ育児支援金が削減されただけの家庭もあるとの声が記されています。そこで、金銭支給に代わる直接的な支援制度を創設できないか伺います。たとえば東京都品川区では、赤ちゃんのいる家庭に毎月おむつなどを届ける「見守りおむつ定期便」を実施しています。この制度は物品支給だけでなく、毎月の訪問によって子育て相談もできる伴走型支援です。こうした制度は保護者の安心感を高めるとともに、町外への魅力発信や定住促進にも効果があると思います。池田町でも、削減された祝い金に代わる継続的かつ伴走型の子育て支援制度を検討する考えはないか伺います。
町長 本町では、国の制度に加えて独自の「こども・みらい事業」として、経済的支援と伴走型支援を再構築しました。その中で、平成27年度から行ってきた出産祝い金・育児支援金は、児童手当の拡充など国の支援が厚くなったことを踏まえ、令和6年度末で廃止しました。代わりに、第2子以降の保育料・給食費の完全無償化、妊婦訪問時の「育児パッケージ贈呈」、産後ケア事業の拡充などを行っています。また、修学旅行補助や卒業祝いプロジェクトなど、子育て全体を見据えた施策も進めています。見守りおむつ定期便については、環境の変化や外出しにくい状況により孤独や不安感を抱えやすい乳児を養育する家庭を定期的に訪問し、不安や心配事への声かけ、養育者と乳児の見守りを行うことを主の目的として実施している事業と認識しています。本町でも保健師・助産師らが妊娠期から出産後まで一貫して支援しており、小規模自治体だからこそ可能な顔の見える伴走支援体制を築いています。
さらに、旧利別小学校跡地に子育て支援施設を整備し、令和9年度の開設を目指しています。今後も全ての子供が安全で豊かな環境で育つことができる社会を目指し、妊娠、子育て世代の方が抱える困り事やニーズを丁寧に酌み取り、子供や養育者の視点に立った柔軟かつ多様な支援策の提供を整えていけるよう関係機関などとも連携を図り子育て支援策の充実に努めていきたいと考えています。
片山 池田町のような小規模自治体ではきめ細やかな支援が可能です。ただ、祝い金がなくなったことで「誰でも一目で分かる支援」がなくなった点が影響していると感じます。
見守りおむつ定期便のような仕組みには2つの大きな利点があります。
- 継続的な経済支援ができること。
- 制度がわかりやすく、町内外に発信しやすいこと。
たとえば、過去の祝い金制度では第4子までで最大70万円の支給でしたが、それに対して見守りおむつ定期便と似たような仕組みであれば、仮に1人当たり4000円相当の商品を2年間提供した場合でも年間4万8000円、2年で総額9万6000円です。これが4人となってそれを3年実施したとしても年間4万8000円が4人、それが3年合計57万6000円となり、町の負担を軽減しつつ、分散しつつ、継続的にこの相当金額の経済的支援が可能です。予算規模としても見通しが立てやすく、従来の一時支給型と比べても分散型施策のため歳出への影響も抑制できます。さらに「町から毎月必要なものが届く」という見える支援は、町外にも印象的に伝わり、「池田町で子どもを育てたい」と思ってもらえる効果があります。
このように経済的・発信的効果を兼ねたわかりやすい制度化は、今の町に必要だと思いますが、町長はどうお考えでしょうか。
町長 今回の質問で御提案いただいた、東京都品川区の「見守りおむつ定期便」は、継続的な経済支援としてわかりやすく、町内外への発信効果が高い「見える伴走型支援」であると受け止めています。
もともと出産祝い金・育児支援金につきましては、子育て支援策としての有効性に正直なところ疑問を抱いていました。子育て世帯を増やすという観点からは、これらの支援金は費用対効果が低いのではないかと考えていたためです。
しかし、私どもが目指すのは単に目を引く制度ではなく、子育てしやすい町を実現する「実質的な子育て支援」であるべきだと考えています。国の児童手当拡充などの制度見直しも踏まえ、今回、見直しを行いました。具体的には、第2子以降の保育料無償化、保育園・幼稚園での給食費完全無償化など、実際に保護者の皆さまの経済的負担が発生する場面で、行政として確かな支援を講じることが負担軽減につながると判断しています。忘れがちではありますが、最大の負担軽減策の一つとして、本町が管内に先駆けて実施した「18歳までの医療費無償化」も挙げられます。医療費という明確なコストに対して確実に支援を行うことは、子どもたちのライフステージ全体を見据え、必要なタイミングで適切な支援を行ううえで望ましいと考えています。これらは、町独自の「こども・みらい事業」として総合的に拡充してきた経緯があります。
また、見守りおむつ定期便のような伴走型支援につきましては、本町でも保健師・管理栄養士・助産師が中心となり、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して顔の見える関係を築いています。本町の出生数は年間20~25名程度で推移しており、小規模自治体ならではのきめ細かな支援体制が機能しているところです。なお、明石市の取組事例(泉元市長の著書等で紹介)では、大型のおむつを玄関先で手渡しすること自体に意義があり、必要に応じて子どもの様子を把握できるという点が強調されています。こうした手法は、各自治体の実情を踏まえ、「伴走型支援として何が必要か」を検討した結果であると理解しています。
私は「スクラップ・アンド・ビルド」ではなく「ビルド・アンド・スクラップ」という考え方を重視しています。すなわち、新たな事業を積み上げながら、既存事業を改めて点検し、優先順位を付け、より効果が期待できるものから着実に取り組むという姿勢です。今回の見直しも、そうした方針のもとで行ったものです。結果として議員指摘のようにわかりやすさというところで少し劣っているのが今回の支援であれば、そこはしっかりとその支援制度を、まだ今年初年度でありますけども、来年度以降に向けてそういったことの広報もしっかりとしていきたいと思っています。
片山 私も一時的な祝い金より、継続的な支援のほうが望ましいと思っています。特に育児用品の支援はすべての家庭で必要であり、税の使い方として「より多くの人に届く支援」に優先的に充てるべきだと考えます。現行の支援は条件付きのものも多く、子どもが生まれた直後の不安な時期に「町が見守ってくれている」と感じられる制度が必要です。その意味でも、全家庭に効果が及び、町の注目度も高める施策は今後優先的に充実させるべきだと思いますが、町長の見解を伺います。
町長 お考えはよく理解できます。私も「広く効果的な支援であること」が重要だと考えています。
ただ、個別の施策ごとの効果よりも、子育て期全体のライフステージを見据えた総合的な支援の成果を重視しています。もちろん、支援策は時代やニーズに応じて見直すべきものであり、今後も必要に応じて検討していきます。祝い金のような制度を設けている自治体は多いですが、池田町はあえて別の方向性で手厚い支援を行っていることを丁寧に伝えていきたいと思います。
今後、町民が実際に「支援が届いている」と実感できるよう、継続的に検証と改善を進めていきます。
エアコン設置補助金の創設について
片山 近年、池田町でも猛暑日が増え、今年7月には35度を超える日が複数回ありました。気象庁のデータを見ても、ここ10年で25度以上の日は約1.5倍、30度以上は2倍、35度以上は3倍に増えています。
町内の公共施設ではエアコン設置が進み、クーリングシェルターも整備されていますが、移動が難しい高齢者の方々にとって、外出して避難するのは現実的ではありません。そのため、自宅にエアコンがない、または古い機種を使用している高齢者世帯などに対して、エアコン設置を支援する補助金制度を創設すべきではないでしょうか。猛暑は一時的な気象現象ではなく「災害」として考えるべき状況です。北海道内では上士幌町や歌志内市で同様の制度があり、補助率50%・上限5万〜7万5,000円の支援を行っています。池田町も高齢化率が高く、国の給付金対象が全体の3分の1にのぼったことを踏まえると、もう少し手厚い支援も検討できると思います。長期的な制度でなくても構いません。数年間の限定でも、命と健康を守るために必要な支援として実施するお考えはありますか。
町長 気候変動への適応策の一つとして熱中症対策の強化が全国的に進んでいます。池田町でも公共施設をクーリングシェルターに指定し、熱中症警戒アラート発令時には施設を開放するなどの取組を行っています。熱中症による死亡者の多くは高齢者で、暑さやのどの渇きを感じにくく、汗をかきにくい体質のため、自覚のないまま重症化するリスクが高いといわれています。そのため、今年7月22日に警戒アラートが発令された際には、独居の高齢者32名に電話で健康確認や予防の呼びかけを行いました。結果、約7割の家庭にエアコンが設置されていましたが、「自分は大丈夫」と考える方が多く、周囲からの声かけの重要性を改めて感じています。一方で、人的対応には限界があり、シェルター利用にも移動手段などの課題があります。過去にもエアコン設置補助を検討したことがありますが、ニーズの把握が難しく、財源面の課題から制度化には至りませんでした。しかし、熱中症予防のためにはエアコンの設置と適切な使用が有効であることから、他自治体の補助内容を参考に、補助制度のあり方を検討していきたいと考えています。
決算審査特別委員会
1)企画振興事務事業18節「地域間幹線系統確保維持事務補助金」
質疑 令和6年度予算では2,700万円が計上され、決算では3,000万円に補正されています。令和7年度予算では2,900万円と増加傾向にあります。単に補助金を拠出するだけではなく、公務での移動利用や高齢者の外出支援など、町民の利用促進につながる新たな施策を行うことで、公共交通の持続可能性を高めることができると考えます。そうした取組や仕掛けについて検討されたことはありますか。
答弁 地域間幹線系統確保維持に対する補助金は、十勝バス「帯広-陸別線」に係る沿線負担金であり、池田町の負担金として計上されています。利用促進策についてですが、別事業となる「地域公共交通計画」の策定において検討を進めています。具体的には、JRや十勝バスと町のコミュニティバスとの接続性を高める取組で、たとえばJRや十勝バスで通学する生徒に対応するため、池田高校までのバス路線を設定し、コミュニティバスとの連絡を図ってきました。これはここ2年ほど継続して実施しているところです。また、新型コロナの影響が落ち着き、乗客数がコロナ前の水準に戻りつつある一方で、人件費や経費の高騰により沿線負担金は増加しています。そのため、昨年度から十勝管内全体で公共交通、とりわけ幹線系統のあり方を見直す検討を始めております。その中で利用促進策についても協議を進めているところです。池田町として具体的に取り組んだ内容としては、池田高校通学に関わる利便性向上が挙げられます。今後も引き続き、利用促進策に努めていきたいと考えております。
2)移住促進事務事業11節「移住プロモーション動画及び動画撮影(春・夏)」
質疑 移住相談やこのプロモーション動画に関して、実際に移住につながるような直接的な実績はあったのでしょうか。また、令和7年度予算には計上されていなかったと思いますが、パンフレットよりも映像のほうが情報量も多く、町の魅力を効果的に伝えることができると考えています。予算上の制約はあるかと思いますが、四季を通じて定期的に映像を発信することで、継続的な移住促進につながる可能性があると思います。こうした継続的な取組についての可能性や課題について、どのようにお考えでしょうか。
答弁 まず、四季を通した映像撮影については、令和5年度に秋・冬、令和6年度に春・夏と、2か年に分けて実施いたしました。これらの映像は移住フェアにおいて池田町を紹介するPR映像として活用していく予定であり、またホームページでも活用できればと考えています。
継続的な取組についてですが、映像の撮影に加えて雑誌広告なども併用しながら町のPRに努めたいと考えております。一方で課題としては、移住フェアに来場される方々からは「就職」や「冬の生活」に関する相談が多い状況にあります。来場者は比較的30代・40代が中心と聞いておりますので、移住後の就職につながるような町としての支援策をどのように整えていくかが、一つの課題であると認識しております。
3)住環境整備事務事業7節「子育て世帯住宅取得応援奨励金」
質疑 令和6年度は町外から1件、町内から2件の交付があったとのことです。件数としては少数ですが、実際に利用があったことは意義があると考えています。移住・定住促進や子育て世帯支援の観点から、この事業の効果をどのように評価しているのか、また今後件数を増やすための課題や対応についてどのようにお考えでしょうか。
答弁 申込み件数自体は多くはありませんが、確実に「子育て世帯を池田町に呼び込む」という点で成果を上げていると考えています。件数の多寡だけでなく、このような施策があることで「池田町は子育てに力を入れている」という強いメッセージを発信できており、今後の拡大にもつながると確信しています。そのため、引き続き本事業を継続していきたいと考えています。今後件数を増やしていくためには、町内外の工務店や建築業者と連携した積極的なPRが必要だと考えています。広報いけだ等を活用して町内の方々に周知を図ることはもちろんですが、町外にも情報を発信していくことが重要です。具体的な方策についてはさらに検討が必要ですが、このままの形でよいとは思っておりませんので、町内外への広告や広報の強化に取り組んでいきたいと考えています。
4)ふるさと寄附促進事務事業7節「報償費」
質疑 本町のふるさと納税は大きな成果を上げています。今後さらに寄附額を伸ばしていくためには、返礼品の拡充や情報発信の強化、他自治体との差別化が課題になると考えます。そこで、今回の決算を踏まえて、今後どのような基本方針で取り組んでいくのか。また、寄附収入を安定的に確保するために重点的に力を入れる分野や新たな取組について、どのようにお考えか伺います。
答弁 ふるさと納税については、継続してご寄附をいただけるような取組が重要と考えています。令和6年度は約11億9,000万円の寄附をいただきましたが、これがさらに13億円、10億円と伸び続けるかというと、正直なところ難しい部分もあります。その理由の一つは返礼品の原料確保です。新聞報道にもありましたが、人気返礼品の一部で原料調達が難しく、産地を切り替えざるを得ないケースも出てきています。原料が安定すれば寄附額も伸ばせますが、現状は難しい状況にあります。しかし、それで立ち止まるわけにはいきません。新たな取組の一つとして、十勝ワインのPR強化を進めています。特に年末の駆け込み寄附が多いことから、「寄附から3日以内に年内発送できる」という体制を整え、都市部を中心とした需要に応えようとしています。これにより大幅な増収は見込みづらいですが、既存の特産品を最大限活用する取組だと考えています。また、近年は「お試し寄附(1,000円寄附)」が大きく伸びています。寄附者は気軽に試し、その返礼品をきっかけに他の返礼品や寄附額全体が伸びる傾向にあります。池田町の特産品をどう活用していくかが、大きな課題と認識しています。さらに、本町では行政と事業者が直接連携して商品開発や課題抽出に取り組んでいます。すべてを外部委託する自治体では担当者の関与が薄くなりがちですが、直営的に関わることは大きなメリットだと考えています。今後もこの体制を強化しながら、新たな返礼品の開発や情報発信に努めてまいります。
5)賦課徴収事務事業18節「相続登記支援補助金」
質疑 令和6年度予算の9割が執行され、多くの町民の方に利用されていると理解しています。この制度の進捗状況として、町内における相続登記は順調に進んでいるのか。また、今後の需要の見込みをどのように把握しているのかを伺います。
答弁 相続登記が必要な物件は数多く存在すると認識しています。資産税係では毎年、納付書を送付していますが、その際「相続人代表者宛」となっているケースがあり、そうした方々を対象に昨年度は「相続登記支援制度があります」といった案内を行いました。その結果、ある程度件数を把握できています。申込み率自体はそれほど高くはありませんが、全体で数百件ある中で、昨年度は90件弱の申請があり、一定の進捗が見られると考えています。今後についてですが、人は必ず寿命があり、その度に相続登記の発生は避けられません。近年では、亡くなられてすぐ補助金を活用して相続登記を行う方も増えており、重要な取組だと認識しています。ただし相続には財産問題が絡み、スムーズに進まない場合もあります。長期化すると子や孫に課題を引き継いでしまうため、なるべく早期に整理していただけるよう、納付書や広報いけだ等を活用して周知・啓発を行ってまいります。今後も申請件数は増加傾向にあると見込んでいますが、相続未登記の件数そのものをできる限り増やさないよう、引き続き取組を進めていきたいと考えています。
6)老人福祉事務事業7節「介護人材就労支援金」
質疑 令和6年度予算では想定人数の7割弱の実績となっていますが、介護人材の確保という観点から現状をどのように評価されているでしょうか。また、介護職員の獲得につながる取組について、現在必要な状況とお考えかどうかも併せて伺います。
答弁 介護人材就労支援金については、支援金があることによって就労がどの程度増加したかという検証までは至っていません。ただし、就労の可否は各事業所の就労条件や給与・待遇面に大きく左右されると認識しています。そのため、事業所単独で十分な支援を行うことは難しく、町として一時金の形で就労支援を行っているところです。新しく職場に就く方にとっては、就労準備の負担を軽減できる制度として喜ばれている実態があります。また、令和7年度には就労支援金を若干拡充しました。
介護や医療、保健分野において、奨学金返済に関する支援制度を設けられないか検討も行いましたが、町全体でより大きな枠組みで議論すべきとの判断により、実施には至っていない状況です。
7)子育て支援事務事業19節「ファミリーサポートセンター事業」
質疑 執行額や利用者数はいずれも少数にとどまっています。これは需要そのものが限られているのか、それとも周知や利用促進の工夫が不足しているのか、どのように認識しているのかを伺います。
答弁 ファミリーサポート事業は、子育てを地域で支え合う仕組みで、子育てのサポートをお願いしたい方を「依頼会員」、サポートしたい方を「提供会員」として登録いただき、必要に応じて保健子育て課が仲介して会員を紹介する制度です。対象は町内在住の生後6か月から小学6年生までのお子さんとなります。利用の際には依頼会員が提供会員に所定の料金を支払う仕組みですが、令和6年度からは住民税非課税世帯などに対して費用の一部を助成し、負担軽減を図っております。しかし、令和6年度の利用は1世帯にとどまり、実績が非常に少ない状況です。要因としては、制度そのものの認知度不足や手続きの煩雑さに加え、面識のない人に子どもを預けることへの心理的ハードルが大きいと考えています。こうした課題を踏まえ、本事業は子育て家庭が困ったときに支え合える重要な取組と位置づけていますので、今後は広報の強化に努めるとともに、利用しやすい仕組みづくりや、安心感・信頼感を「見える化」する工夫を進め、多くの子育て家庭に気軽に利用いただける制度を目指して検討してまいります。
8)健康教育相談訪問事業13節「子育て支援サービスアプリの使用料」
質疑 このアプリの利用率はどの程度あり、支出した使用料に見合う成果が得られているのでしょうか。子育て世帯への支援という目的に対して、どのような効果を発揮していると評価しているのかを伺います。
答弁 現在「子育て応援ナビ」というアプリを使用しております。利用率という形では数値を出していませんが、登録者数は令和7年9月現在で260名となっています。令和2年度の開始当初は134名であり、年々増加傾向にあると考えています。主な活用内容としては、予防接種のスケジュール管理や、子育てイベント・子育て支援サービスの情報提供などをタイムリーに発信できる点で効果を感じています。
一方で、双方向のやり取りができないこと、また登録者の詳細が不明であることから、個別通知の代替とはならないという課題があります。今後は、アプリのより効果的な活用方法について、他町の事例も参考にしながら検討していきたいと考えております。
9)農地利用促進事務事業
質疑 農地の権利移動の状況を踏まえ、農地の利用集積は当初の計画や目標と比較してどの程度進んでいるのでしょうか。また、非耕作地の推移とあわせて、農地が有効に活用されているかについて、町としてどのように評価しているかをお聞かせください。
答弁 利用集積計画については、北海道全体で特に進展が見られており、計画以上の進捗となっています。池田町においても同様に、当初計画を上回る形で利用集積が進んでいる状況です。
10)林業推進事務事業12節 森林教育委託料
質疑 成果について、また今後の継続の必要性や見通しについてお聞かせください。
答弁 森林教育委託料については、幼稚園・保育園から小中学校までを対象に実施しており、森林に親しむという観点から一定の成果があったと考えております。決算額は総額約680万円、約700万円近くとなっており、これは譲与税充当事業の約15%を占め、全体の充当事業の中では2番目に大きな支出額となっています。令和6年度については、譲与税の歳入額を支出が上回ったため、年度末には積立基金を取り崩す結果となりました。今後の見通しについては、引き続き検討中であり、現時点で明確な方向性は定まっていない状況です。
11)産業活性化補助金について追加質疑
質疑 30万円以上の申請にあたってプレゼンテーションを行う仕組みになっていますが、この制度は事業者にとって心理的・実務的なハードルが大きいと感じています。実際に、この仕組みが申請を抑制している、あるいは「プレゼンが必要なら断念する」といったケースはなかったのでしょうか。また、国の産業活性化補助金や事業再構築補助金などは基本的に書類審査であり、採択枠が限られた競争的な仕組みでもあります。それに比べ、町の補助金でプレゼンを課している点については、むしろ利用しづらい制度設計になっているのではないかと感じています。今後は新規事業者向けに限らず、より使いやすく、チャレンジしやすい補助金制度に改善していくお考えはあるでしょうか。
答弁 令和6年度において、申請後に「プレゼンがあるので取り下げる」といった事例はありませんでした。ただし、申請の手間や負担を大きく感じている方もいるかもしれません。一方で、このプレゼンの場は補助金等審査委員会に対して、自分のやりたい事業を直接アピールできる機会でもあると考えています。書類審査だけでは伝わりにくい、事業者自身の考えや町内への波及効果を、自らの言葉でPRできる点は重要だと思っております。そのため、現時点でこの仕組みを見直す予定はありません。
また、この補助金は採択枠が限定された競争的な制度ではなく、町としてできる限り多くの事業者に活用していただきたいと考えています。自分の事業拡大や新規起業に向けて積極的にPRし、ぜひ利用していただきたいというのが町の基本的な姿勢です。
12)中小企業融資事務事業18節
質疑 借入れによるものであっても、運転資金であれば必要運転資金分、設備投資であれば減価償却分程度の資金を手元に確保することは、事業継続性の維持に直結し、町内事業者にとって大きな意義があると考えています。報告書にある融資状況を踏まえ、この制度は必要とする事業者に十分に活用されているのか。また、より多くの事業者に活用してもらうための働きかけについて、どのようにお考えでしょうか。
答弁 令和6年度の融資実績は、総額で約2,500万円となっており、額が増加していることから一定程度活用が進んでいると考えております。一方で、融資は当然ながら償還が伴うため、積極的に活用するかどうかは事業者ごとの判断に委ねられる部分が大きいと認識しています。町としては、制度の存在や活用方法について周知の工夫を検討していきたいと考えておりますが、最終的には各事業者が事業計画や資金繰りを踏まえて判断することになると考えています。
13)中学校運営管理事業17節
質疑 備品購入費の中で電子黒板6台が計上されていますが、現在有効に活用されているのでしょうか。具体的にどのように使用されているのか。また、今後必要と考えられているデジタル機器にはどのようなものがあるのかを伺います。
答弁 電子黒板については、中学校の普通教室に小型(65型程度)のものを設置し、美術や理科などの授業で活用しています。特別教室については横に広く奥行きもあるため、大型の電子黒板を配置し、遠くからでも視認できるように活用しております。今後の展望についてですが、今年の夏に実施した「サマーレビュー」において、鳥取の小中一貫義務教育学校(分離型先進校)を視察した際、同校では小学校部門・中学校部門いずれにおいても電子黒板を全教室に配置している事例を確認しました。池田町においても、学校現場から同様の要望が出ており、今後は全体予算の中で調整しつつ、必要な機器の導入について検討を進めていきたいと考えております。
14)郷土資料保存事務事業
質疑 郷土資料館の維持経費として支出されていると思いますが、より多くの人に来館してもらうための仕掛けや取組に必要な経費は、実際の運営の中で必要とならなかったのでしょうか。
答弁 特別展の開催など、工夫をしながら運営を行ってきました。その際に必要となる経費については、消耗品等を含め、展示に必要な費用を支出しております。
15)ブドウ・ブドウ酒事業の損益計算書
質疑 令和6年度予算では3,700万円の損失を見込んでいましたが、結果としては660万円にとどまりました。その主な要因をどのように分析されていますか。
答弁 当初予算では、収入・支出ともに厳しめに見積もっていたため不用額が生じました。また、大きな要因としては、50周年事業においてドリカム様によるミニライブが行われ、大きな注目を集めたことで売上が好調となり、収入増につながった点が挙げられます。
16)ブドウ・ブドウ酒事業会計のキャッシュフロー計算書
質疑 期首時点では期末資金減少額を約7,800万円、期末残高を約5億8,000万円と見込んでいましたが、実際には期末資金が約7,100万円増加し、期末残高も約7億6,000万円と、約1億5,000万円の改善となっています。大きな改善だと考えますが、その要因をどのように分析されているのか。また、この改善には設備投資の先送りや未払経費の計上といった要素も含まれているのかを伺います。
答弁 資金増加が大きくなった要因についてですが、当初予算では収益を厳しめに、費用については不足を懸念して余裕を持って積算しておりました。その中で特に大きかったのが原材料費で、ブドウの収穫量を基に予算を組んでいましたが、令和6年度はワイン専用品種の収穫量が平年並みであったこと、またキャンベルやヤグラといった加工用ブドウの買入数量が減少したことにより、費用が抑えられました。加えて、ワイン城50周年事業によって売上が好調であったことも収入増につながっています。これら二つの要因が大きく働き、資金増加額が想定より大きくなったと考えております。なお、投資的経費については突発的な案件もあり、予定どおりに進まない部分もありますが、優先順位をつけながら設備導入や修繕を進めているところです。
17)ブドウ・ブドウ酒事業会計の棚卸資産残高
質疑 近年は前年度比で在庫が増加する傾向にありましたが、令和6年度は2,300万円の減少となり、キャッシュフローにも影響があったと考えます。これは生産状況の問題によるものなのか。もしそうであれば、令和7年度の営業や販売計画に支障が生じる可能性はあるのか、あるいは既に影響が出ているのかについてお聞かせください。
答弁 農産物を原料とするため計画どおりにはいかない部分があります。令和5年度の生産量が少なかったことに加え、令和6年度の生産量も少なかったため、令和5年度に生産した製品が売れて在庫が減少した、という要因が大きいと考えています。売上が好調であったことも事実です。
今後については、計画的な予算編成を行っているものの、農産物の性質上、正確な予測が難しい点があります。そのため、より適切な積算方法を研究していきたいと考えております。いずれにしても、安定的に純利益を確保できるよう努めてまいります。以上です。