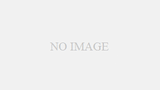令和7年6月に開催される定例会関係の投稿です。
一般質問
一般質問の内容
質問事項 地域活動における情報発信と支援について
片山議員の質問
地域活動やボランティアについて伺います。中学生や高校生、そして社会人を対象としたボランティア活動や地域イベントは、世代を問わず人とのつながりを実感できる大切な活動です。中高生にとっては社会性や主体性を育む教育的価値も高いと思います。そこで、町として情報を集約・発信すること、ボランティア保険の加入を支援すること、公認団体の情報共有の仕組みを整備すること、この三点について町長の所見を伺います。
町長の答弁
ボランティアの育成や活動支援は、核家族化、人口減少、高齢化が進む本町において、地域福祉の基盤を整えるうえで重要な視点であると認識しています。本町では、昭和57年4月に社会福祉協議会が池田町ボランティアセンターを開設し、ボランティア活動の促進を目的として、相談・登録・活動紹介などを行ってまいりました。令和7年4月時点での登録は、団体が29、個人が265名となっておりますが、平均年齢は69.2歳と高齢化が進んでおり、若い世代への広がりが課題となっております。
まず、町による情報の集約・発信についてですが、ボランティアに関する情報は一元的に管理されることが望ましく、本町ではボランティアセンターがその役割を担っております。他の自治体においては、ボランティア募集情報をホームページに掲載することで、関心を持つ方が参加しやすい環境を整えている自治体もある。本町においても、町ホームページの活用を含め、発信内容の充実や情報の集約、周知の方法について、今後検討していく必要があります。
次に、ボランティア保険の加入支援についてです。ボランティア団体は、登録と同時に保険に加入しており、その保険料は社会福祉協議会が負担しています。財源には町からの交付金を活用しており、今後もこの支援は継続して実施する予定です。
最後に、公認団体の情報共有の仕組み整備についてです。学校支援ボランティアを含むボランティア団体の情報は、社会福祉協議会のホームページに掲載されておりますが、今後は先進事例を参考に、より分かりやすく、参加しやすい支援の在り方について、ボランティアセンターと連携しながら検討してまいります。
なお、ボランティア活動を含む地域活動については、他の自治体において、自主的な住民活動全般を対象として行政が支援する事例もございます。本町においても、「協働のまちづくり」の推進に向けて、こうした手法を研究し、適切な支援のあり方を検討してまいりたいと考えております。
片山議員の質問
ボランティア情報の発信については、社会福祉協議会が運営するボランティアセンターが担っているとの答弁でした。しかし、そこに集約されている情報は主に福祉分野に限定されているのではないでしょうか。集約発信する情報については、福祉ボランティアだけにとどまらず、様々な町民活動、NPO、少年団活動や、自治会町内会の活動といったもの、それから例えば町内の公共施設を活用した民間事業者のイベントの事業についても、例えば「今月はこういったイベントがあります」「このボランティアを募集しています」といった情報を広く発信する場が必要ではないでしょうか。
これらの多様な活動を一元的に集約・発信できるような仕組みを、ボランティア情報に加えて整備することは可能だと考えます。先ほどの答弁では「先進事例を参考にしながら研究する」とのことでしたが、町内ではすでにさまざまな分野で積極的に活動されている方々もおり、活動同士の横のつながりもあります。情報が「見える化」されることで、偶然その情報に触れた町民が新たに活動に加わり、さらに別の活動へとつながっていくという好循環が期待できます。
研究だけにとどめるのではなく、まずは小さな規模でも実際に取り組みを始めることで、結果的により実効性のある効果的な地域活動支援へとつながっていくと考えますが、この点について町長の所見を伺います。
町長の答弁
対象となる団体や活動は多様であり、情報発信のあり方も工夫が必要です。現在は、行政の中でそれぞれの活動を担当する部署が異なり、支援も分かれています。ですので、今すぐに集約的な支援体制を構築するのは難しいというのが現状です。ただ、少子高齢化の中で担い手不足が深刻化しているのも事実であり、協働のまちづくりを進めていく上で、地域活動をどのような形で支援をしていくのかといったところをしっかりと整理をした上で、検討、検証をしていきたいと考えます。
委託事業の内製化の強化と職員研修等の取組について
片山議員の質問
池田町で作成される長期計画について、これまで外部委託に依存しすぎず、一定程度は職員の関与が図られてきたとは思いますが、今後はさらに町職員自身が中核部分を担う必要があると考えます。実際に町の実情や課題を一番理解しているのは、住民と日々接している職員の皆さんです。
文書のレイアウトやアンケート集計などは外部の力を借りるのが合理的ですが、政策の立案や分析などの中核部分は職員の知見で進めていくべきです。職員の企画力や政策立案力を高める研修も含めて、外部委託の活用方針や職員育成の取組について、町長の所見を伺います。
町長の答弁
町の計画策定は基本的に担当課が主導しつつ、必要に応じて外部へ業務委託する形で進めています。たとえば、第5次総合計画の策定時には、外部委託は住民アンケートの分析のみでしたが、反省点もあり、今年度の中間見直しでは前期計画の検証や、住民意見の計画への反映において業務委託としています。
なお、各種データ収集事業者ヒアリング、住民アンケート調査のほか、計画素案の作成、計画検討会議や、住民説明会での説明支援など、計画策定に係る事務全般を業務委託するものもありますが、このことにより、町の意思決定が必要な内容の検討に注力する時間を確保し、さらには委託業務としての経費区分により、補助事業の活用が可能となるなど、行政コスト面の効果が期待できるものでもあります。
外部委託の方針は現在、統一された基準は設けておらず、計画の性質ごとに判断しています。また、職員研修については、北海道庁への派遣や自治大学校、市町村職員中央研修所などへの参加を計画的に進めています。昇格研修や実務研修に加え、政策形成分野への参加も今後はさらに強化していく方針です。
片山議員の質問
委託の進め方によっては、形式的な素案が提案されて町がそれに修正を加えるだけの「形だけの計画」になってしまう危険性もあると思います。町の現状や実態に合った実効性ある計画とするには、やはり外部に任せる範囲と、町職員が担うべき部分の「線引き」が必要ではないでしょうか。明確な基準を設けるべきだと思いますが、町長の所見を伺います。
町長の答弁
外部委託を行う際には、その内容や委託範囲によって、最終的に計画の活用面で課題が発生するのではないかといった意味で一定の線引きが必要でないか、という御質問だというふうに認識をします。特に、専門的な知見や客観的な分析が必要な業務については、外部に委ねるところも多いと思います。ただし、外部委託の目的は決して経費削減だけではありません。計画そのものの質を高めること、そしてその実効性を確保することが最も重要だと考えております。そのためには、職員自身が主体的に関与することが不可欠であると強く認識しております。
議員ご指摘の「線引き」についてですが、「ここからは外部」「ここからは職員」といった明確な基準は、現時点では設けておりません。それぞれの計画の特性や状況を踏まえ、個別に丁寧に判断していくといった考えにあります。
片山議員の質問
外部に頼る部分と職員が担うべき部分、それぞれを明確にしつつ、職員の政策立案力を高めていくことが重要だと考えます。たとえば自治大学校などでの研修は、政策形成や行政管理能力の向上に非常に有効ですが、今年度の予算にはその派遣費が計上されていなかったかと思います。
予算340万円ほどが職員研修にあてられているようですが、職員数や業務の幅広さを考えると少し手薄に感じます。町職員の育成のため、もっと手厚い研修予算が必要ではないでしょうか。
町長の答弁
ご指摘のとおり、職員研修の充実は非常に重要です。自治大学校は大変有意義な研修ですが、期間が長いため派遣先の業務への配慮も必要で、今年度は見送り、来年度以降の派遣を予定しております。限られた職員数の中でも、専門性と総合力の両方を高めるため、可能な限り積極的に研修の機会は確保してまいります。
片山議員の質問
自治大学校などの派遣研修に加え、今はオンラインでも多様な研修を受けられる時代です。たとえばDXの進展を活かし、役場内でもオンライン研修が可能な環境を整えることで外に出ることなく学べる機会がもっと増やせるのではないでしょうか。
ただしオンライン研修でも無料ではないものも多く、予算措置も必要です。今後、こういった手法にも予算を振り分けていく考えはありますか?
町長の答弁
ご指摘のとおり、職員研修にはさまざまな形態がございます。近年では、オンラインで受講可能な研修も増えており、本町としてもそうした機会を積極的に活用できるよう努めているところです。こうしたオンライン研修の多くは無料、または非常に低コストで提供されているため、予算上に見えた形にはなっていませんが、職員研修全体については、年度ごとに研修計画を策定し、それに基づいて積極的に実施しているところです。今後も、対面・オンラインを問わず、職員のスキルアップに向けた取り組みを一層強化してまいります。
地域おこし協力隊と地域をつなぐ仕組みづくりについて
片山議員の質問
地域おこし協力隊について、町民の方々から「誰が来ていて、何をしているのかよくわからない」との声を私自身もたびたび耳にします。町では広報紙やSNSで情報発信をしていますが、実際には十分に伝わっていないように感じています。
この制度は国の予算も使われており、説明責任の観点からも、もっと踏み込んだ情報発信が必要です。たとえば、協力隊の方が「自分はどんな人で、今どんなことをしていて、これから何を目指しているのか」などを、町民に直接伝える場を定期的に設けることはできないでしょうか?運営は行政がサポートしてもいいですが、内容や進行は協力隊本人が中心になることで、町民にも伝わりやすくなりますし、協力隊側にとっても活動理解や支援の獲得につながるはずです。
また、協力隊は任期後に町に定住し、地域の担い手になってくれる可能性もあります。だからこそ、今のうちから町民との接点を増やし、相互理解を深める仕組みを作ることが、将来的に町の力になると考えます。町長のご所見を伺います。
町長の答弁
地域おこし協力隊は、都市部から過疎地域に移住し、地域活性化に取り組む国の制度で、町にとっても将来的な定住・定着を期待できる大切な人材です。本町では平成27年に受け入れを開始し、令和7年6月現在、任用型8名、委託型1名の計9名が活動中です。
協力隊の活動については、毎月発行の『広報いけだ』に専用コーナーを設けて紹介しているほか、インスタグラムやフェイスブックでも各隊員が情報を発信しています。これは総務省の推進要綱にも基づいた取組で、一定の情報提供は実施しているところです。
また、今年3月からは町の担当課と協力隊が月1回の定期ミーティングを行っており、その中で協力隊の方から「活動報告会を開きたい」との提案がありました。現在、その企画を協力隊自身が主体となって進めており、11月頃の開催を目指しています。具体的には、今年2月に2名の隊員が参加した「地域おこし協力隊全国サミット」で紹介された映画の上映会と、協力隊それぞれによる活動報告をセットにしたイベントを予定しています。この場を通じて町民との交流を深め、新たな関係づくりにつなげたいという意図があります。
町としても、有意義な機会になるよう支援を行う考えですし、開催の際は、多くの町民の皆さんに参加いただき、協力隊との交流が深まることを期待しているところです。今後はこの報告会を年1回程度の定期開催として検討しています。こうした取組を通じて、協力隊の活動がより町民に伝わるよう、発信の強化に努めてまいります。