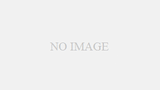令和7年 3月定例会に関連する投稿です。
一般質問
一般質問の要約
池田町産品を活用した商品開発支援の強化について
片山の発言要約
池田町産品を活用した商品開発を積極的に支援することで、事業者の競争力向上や地域経済の活性化につながると主張。ふるさと納税の寄附額が11億円を超え、町への注目が高まる中、開発された商品を返礼品として活用すれば、さらなる寄附増加と地域経済の好循環が期待できると提案。そのため、補助制度の期間延長、補助率の引き上げ、補助金上限額の増額など、より効果的な支援策の導入を検討すべきと訴え、財政負担を抑えつつ支援を強化する方法について町長の見解を求めた。
町長の発言要約
池田町では、平成25年度から地域資源を活用した事業者支援を実施しており、商品開発支援事業もその一環として補助金を交付している。現行制度では補助率は2分の1、上限額は100万円(農商工連携事業は150万円)として運用。補助期間の延長については、年度単位での申請が原則だが、新製品開発には時間がかかるため、年度を区切った補助の可能性を検討する。補助率の引き上げについては、事業者負担の重要性を考慮し、現行の2分の1が適切と判断。補助金の限度額については、物価高騰を踏まえつつ、制度全体の見直しを含め、令和7年度に向けた改正を検討していく方針を示した。
「多世代交流施設ふらっと」の開放時間拡充について
片山の発言要約
多世代交流施設「ふらっと」は子供の居場所として活用できるため、開放時間を拡充すべきと提案。令和7年度の子供の居場所づくり補助金を活用すれば、運営の負担を軽減できる可能性がある。常時開放ではなく、例えば午後の数時間、週2〜3回の短時間開放を実施し、地域おこし協力隊などを活用して柔軟な運営ができないかと町長の見解を求めた。
町長の発言要約
「ふらっと」は多世代の交流を目的とした施設であり、貸館方式を採用している。常時開放には管理人の配置が必要で、費用や安全管理の課題がある。放課後サロンのように活動団体が主体となる形での開放は可能であり、令和7年度の補助金で支援を予定。今後、施設全体の活用を検討し、町全体で子供の居場所づくりを進めていくと述べた。
歩きたくなる町なかつくりについて
片山の発言要約
町の主要道路沿いに芝生やベンチを設置し、街路樹を整備することで、町民や観光客が快適に過ごせる環境を作るべきだと提案。これにより観光客の滞在時間が延び、町の中心部へ足を運ぶ人が増え、飲食店の利用が増加し、地元経済の活性化につながると指摘。また、高齢者や子連れの外出がしやすくなり、健康促進や住民交流の活発化、さらには空き店舗の活用や移住促進にも貢献すると述べる。こうした整備を進めるために、国の補助金を活用し、官民連携でのまちづくりを検討すべきと町長の見解を求めた。
町長の発言要約
町では商工会や町内会の協力のもと、主要道路沿いの景観維持を進めているが、空き店舗や空き地が増え、植樹帯の維持管理が難しくなっている。新年度から町直営や委託管理を強化する方針。芝生やベンチの設置、街路樹の整備は快適な歩行空間の提供に効果的だが、維持管理の負担が増えるため、総合的な計画が必要と説明。また、国の「官民連携まちなか再生推進事業」の補助金は、単なる空き地活用ではなく、町全体の再生を目的とするため、池田町での活用は難しいと判断。今後、町の整備構想を明確にし、適切な補助事業の活用を検討していくと述べた。
一般質問の内容
1.池田町の産品を活かした商品開発支援についての議論
片山議員の質問
池田町の特産品を活かした商品開発を強力に支援することで、事業者の競争力向上や地域経済の活性化、さらには町全体の発展につながると考えます。今年度のふるさと納税額は11億円を超え、町への注目度が高まっています。新たに開発された商品を返礼品として活用すれば、さらなる寄附額の増加が期待でき、地域経済の好循環も生み出せるのではないでしょうか。
この観点から、現在の補助制度について、補助期間を2年程度に延長したり、補助率の引き上げ、補助金の上限額の増額など、より効果的な支援策を講じることができるのではないかと考えます。財政負担を抑えつつ支援を強化する方法について、町長のご意見を伺います。
町長の回答
池田町では、平成25年度から産業活性化事業補助金を交付し、地域資源を活用した商品開発の支援を行っています。現在、補助率は2分の1以内で、上限額は100万円(農商工連携事業の場合は150万円)となっています。ふるさと納税の返礼品としての活用は、地域経済の好循環に寄与する可能性があり、補助制度の拡充は検討に値すると考えています。
補助期間の延長については、新製品開発には時間がかかることから、年度を区切った補助の可能性を検討します。しかし、補助率の引き上げについては、事業者自身の負担も必要であり、現状の2分の1が適切と判断しています。物価高騰の影響も踏まえ、補助金上限額については見直しを含め、令和7年度に向けた制度改正を検討していきます。
片山議員の再質問
物価高騰により事業者の負担が増す中、商品開発には半年以上かかることが多く、小規模事業者にとっては1年以上の補助が必要ではないでしょうか。また、国では小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金で3分の2まで補助しており、池田町でも小規模事業者に対して同様の措置を講じることが望ましいと考えます。まずは試験的に制度を実施し、改善点を洗い出しながら、補助期間の延長や補助率の引き上げを検討できないでしょうか。
町長の最終回答
2か年の事業を想定できるかどうかを検討し、小規模事業者の経営状況を考慮した上で補助率の変更についても慎重に議論したいと考えます。商品開発には設備投資も伴うことが多く、事業者自身の負担を一定程度求めることで、主体的な商品開発を促進する狙いもあります。
また、商品開発には「構想から試作品の製作」と「設備投資を伴う製品化」の2つの段階があり、制度設計の面でも分ける方が望ましい可能性があります。この点も含め、制度全体の見直しを行い、どのような支援策が最も有効かを検討していきたいと考えています。
まとめ 池田町では、特産品を活かした商品開発支援を継続的に行っており、ふるさと納税の返礼品としての活用にも前向きな姿勢を示しています。一方で、補助期間の延長や補助率の引き上げについては、事業者の負担や制度設計の課題を考慮し、慎重に検討していく方針です。今後、制度の見直しや支援策の充実に向けた具体的な議論が進められることが期待されます。
2.多世代交流施設「ふらっと」の開放時間拡充について
片山議員の質問
池田町では、子供が気軽に立ち寄れる居場所の充実が求められています。多世代交流施設「ふらっと」は立地や設備面で優れており、子供の居場所としての活用が期待できます。令和7年度には子供の居場所づくりに関する補助金が新設される予定であり、これを活用すれば「ふらっと」の開放時間を拡充できるのではないでしょうか。
現状の貸館方式だけでなく、例えば小学生や中学生向けに放課後の数時間だけでも開放することで、子供たちの立ち寄りやすい環境を整備できると考えます。地域おこし協力隊の活動拠点としての活用や、既存の活動団体との協力により、柔軟な運営を進めることが可能ではないでしょうか。町長のご見解をお聞かせください。
町長の回答
「ふらっと」は、子供から高齢者まで幅広い世代の交流を促進し、地域共生社会の実現を目的として令和4年に設置されました。現在、貸館方式により運営されており、多くの団体が利用し、その数は年々増加しています。
施設の常時開放については、管理人の配置や安全確保の課題があり、運営費用の負担も大きいため、現状の貸館方式を継続する方針です。一方で、放課後サロンのような活動団体が主体となり、見守り体制を確保する形であれば、開放時間の拡充も可能と考えています。そのため、令和7年度の補助金を活用し、活動団体がより積極的に子供の居場所づくりを担える環境を整備していきます。
片山議員の再質問
開放時間を短時間でも設け、例えば週2〜3回、放課後の時間帯に子供が立ち寄れるスペースを確保することが重要ではないでしょうか。また、貸館方式のみならず、一部の部屋を子供専用のスペースとして開放する方法も考えられます。少しずつ試験的に進め、柔軟な運用を検討していくことが望ましいと考えます。
町長の最終回答
「ふらっと」が子供の居場所として活用されることには大いに賛同しますが、施設の管理や安全確保の面で課題があります。開放時間の拡充については、既存の活動団体や新たな団体と連携しながら、補助金を活用して支援を進めます。また、町全体で子供の居場所づくりを推進するため、今後整備予定の子育て支援施設とも連携しながら、総合的な対策を検討していきます。
まとめ 池田町では、「ふらっと」を子供の居場所として活用する可能性について前向きに議論が進められています。管理上の課題から常時開放は難しいものの、放課後サロンのような活動団体と連携し、開放時間の拡充を支援する方針です。今後、補助金の活用や新たな施設整備と合わせて、子供たちが安心して過ごせる環境づくりを進めていくことが期待されます。
3.歩きたくなるまちなかづくりについて
片山議員の質問
町内の主要道路沿いの環境整備として、芝生化やベンチの設置、街路樹の整備を進めることで、町民や観光客が快適に歩ける環境を作るべきです。年間25万人以上が訪れるワイン城をはじめ、観光客が町の中心部まで足を運ぶようになれば、飲食店や商業施設への立ち寄りが増え、地域経済の活性化につながります。
また、ベンチの設置は、高齢者や子供連れの外出を促し、健康づくりや住民同士の交流の場を生み出します。さらに、人が集まる町になることで空き店舗や空き家の活用が進み、移住促進や新規事業の誘致にも良い影響を与えると考えます。官民連携のまちなか再生推進事業などの補助金を活用し、こうした環境整備を進めることは可能ではないでしょうか。町長のご見解をお聞かせください。
町長の回答
現在、池田町では商工会や町内会の協力により、主要道路沿いの景観維持を進めています。しかし、市街地の空き店舗や空き地が増え、植樹帯の維持管理が困難になってきています。新年度より町の直営や委託業務による管理を強化する方針です。
芝生化やベンチの設置、街路樹の整備は、歩行者にとって快適な環境を提供し、景観向上にもつながるため、有効な施策と考えます。ただし、これらの整備には維持管理の負担が伴うため、町なかの総合的かつ現実的な構想を検討した上で実施する必要があります。
官民連携まちなか再生推進事業の補助金については、道路沿いの環境整備だけでなく、都市の魅力向上や社会実験など広範な取組が求められるため、池田町の活用は難しいと判断しています。今後、町の整備計画を明確にし、適切な補助事業の活用を検討していきます。
片山議員の再質問
未来ビジョンをもとにした大規模な再生事業の実施は難しいかもしれませんが、必要なところから少しずつ整備を進めることは可能ではないでしょうか。例えば、ベンチや街路樹の設置を優先し、町民の生活に直結する環境改善を進めるべきです。高齢者が安心して歩ける町になることで、外出機会の増加や観光客の誘導にもつながります。まずはベンチの設置から取り組むことを検討できませんか。
町長の最終回答
ご提案の通り、できるところから少しずつ整備を進めることは重要だと考えます。官民連携まちなか再生推進事業は大規模な計画が求められますが、町民の意見を取り入れながら、現実的な範囲での環境整備を検討していきます。
また、池田町は通過型の観光地ではなく、町内周遊型の観光を目指すべきだと考えています。そのためにはハード面の整備だけでなく、町の魅力を高めるソフト施策も重要です。町民や観光客が立ち寄りやすい環境を整えるため、ベンチの設置など、まずは実施可能な部分から行うべきかと考えています。
まとめ 池田町の歩きたくなるまちづくりについて、町は前向きに検討を進めていく方針を示したと思います。ハード整備には維持管理の課題がありますが、まずは実現可能な範囲での環境整備を進めることが重要です。今後、町の整備計画の中で具体的な施策が進められることが期待されます。
予算審査特別委員会
1.片山委員の質問:
申請書作成システムの導入によって、町民の利便性がどの程度向上するのか。
答弁者の回答:
全国的に「書かない窓口」が進められており、本町でも住民サービス向上の一環としてDXを推進中である。申請時に何度も住所や氏名を書く必要や、窓口を何度も移動するなどの課題がある。今回導入するシステムは、マイナンバーカード等を用いて申請者情報を読み取り、記入を自動化するもので、町民の窓口での負担軽減を図る。効果の程度は数値化しにくいが、利便性向上は見込まれる。また、町民課や税務課ではすでに一部申請書の統一が進んでおり、今後は「おくやみのワンストップ窓口」の検討も進め、さらに窓口業務の簡素化を目指す。
2.片山委員の質問:
予算書の「ふるさと寄附金促進事務事業」における行事報償費が昨年度より減額されたが、令和7年度にこの予算を使ったイベントを検討しているのか。
答弁者の回答:
行事報償費は科目存置しているが、令和7年度は大手ポータルサイト主催のイベント参加を予定しており、その旅費や出展費用は別の科目(旅費・負担金等)で計上している。ただし、このイベントは抽選制のため、外れた場合には、令和5年12月に開催したワイン城での返礼品見本市のようなイベントを再度行いたいと考えている。経費率(寄附額の5割までという制約)を踏まえつつ、道内の特定エリアで池田町の返礼品の魅力をPRする取り組みを検討中。
3.片山委員の質問:
住環境整備事務事業における「公営住宅リノベーション事業補助金」について、具体的な運用方法・補助率・今後の想定(対象の広がりや方向性)は。
答弁者の回答:
現在使用していない公営住宅を最終的に解体するのではなく、利活用するための制度として補助金を設定する。住居以外にも事務所や飲食店との併用住宅としてのリノベーションも想定している。町内外の人を対象とし、特に町外からの移住者による活用は、産業活性化にもつながる可能性がある。補助率は事業費の2分の1で、上限は400万円。今年度はトライアルとして実施し、実際にニーズがあるかを見極める。老朽化した団地の見栄え改善や再活用も視野に入れており、今後は産官学連携なども含めて、可能性を調査・検討していきたい。
4.片山委員の質問:
「子供の居場所づくり活動支援補助金」について、支援対象となる事業者の規模や想定される事業内容は。また、個人による活動や町内での場所の制限については。
答弁者の回答:
この補助金は、学校や学童以外の「第3の居場所」として、放課後や休日に子どもが過ごせる場を提供する活動を支援するもの。現在は「放課後サロン」として週1回活動する団体があり、その団体への補助が主な想定である。人手や資金が不足している中、活動の継続と発展を後押しする目的である。金額は、他自治体の例を参考に1団体あたり上限10万円とし、当該団体と事前確認のうえ設定している。今年度は2団体分を計上している。個人も対象にはなり得るが、実際には1人での継続的な運営は難しいと考えており、基本は団体を想定。活動場所は町内であればどこでも可とし、現在の活動場所「ふらっと」以外でも対象になる。
5.片山委員の質問:
有害鳥獣防除設備設置事業補助金の大幅増額について、増額の背景や期待される効果(例えば面積や長さなど)。
答弁者の回答:
補助金の上限を従来の5万円から10万円に引き上げたことにより、事業費を増額する。電気牧柵の設置が有害鳥獣対策として有効とされており、駆除と組み合わせることで効果を発揮するとの研修報告もある。ただし、電気牧柵の設置には草刈りや適切な高さの維持などノウハウが必要であり、そうした指導も視野に入れている。全域への設置はコストや維持管理の面から困難だが、専門家の助言を基に、今後の効果を見込んで補助金を増額した。駆除と設備設置の「両輪」で対策を進めていきたい。