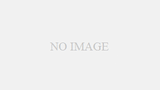一般質問
1.巡回期日前投票所の設置について
質問(片山) 先日行われました10月の池田町議会議員補欠選挙では投票率が45%と低く、それ以前の池田町議会議員選挙においても70%台と、投票率は低い状況にありました。選挙の際には町内各地を回る巡回投票所を設置することで、期日前投票が行える場をふやし投票率の向上を目指すべきであると考えます。現在路線バスを走らせておりますが、効果は非常に限定的なものであり、また、投票の権利というものは憲法で保障された権利でありますので、池田町はその権利を行使できる場を一層ふやす努力も必要であるかと考えます。
選挙管理委員会委員長の所見を伺います。
答弁(選挙管理委員会の委員長) 期日前投票は、選挙投票日に仕事やレジャーなど一定の理由により投票所へ行って投票することができない有権者が投票前でも投票を行うことができる制度です。平成15年公職選挙法の改正により従前の不在者投票に代わって創設され、より簡易的に投票できる制度として有権者にも定着しています。現在、本町における期日前投票所は社会福祉センターの1か所のみであり、交通手段がない高齢者等の投票機会の確保や投票率の向上を目的とし、平日のみではありますが通常運行するコミュニティーバスとスクールバス混乗便の7路線を活用し、投票所までの往復を無料で乗車できる取組を実施しています。
住民周知は行っているものの、利用率については議員御指摘のとおり低い状況で、交通手段がない高齢者等の投票機会の確保については、本町のみならず全国の多くの自治体が抱える課題であると認識しています。そのような状況の中、平成28年4月の公職選挙法の一部改正により、期日前投票における弾力運用として、投票所への移動手段が困難な有権者の投票機会の拡大などを目的に、車両による巡回式の移動期日前投票所、以下、移動期日前投票所といいますが、設置することが可能になりました。十勝管内では、士幌町と大樹町で導入されています。移動期日前投票所は、巡回車両を利用し公共施設や地域の会館などに決められた時間で巡回していく方法もありますが、家族の介助も受けられない高齢者や身体が不自由な方など、自分での移動が困難で、特定の要件に該当する方を対象として巡回車両が自宅に出向いて投票を行ってもらうオンデマンド型を導入する自治体も多く、管内の2町はこの方式を取り入れてます。
先行事例による実施方法ですが、希望する方は事前に申し込みが必要となり、聞き取りにより対象要件に該当する方を決定の上、実施場所と投票時間帯を設定しますが、本来の投票所に加え、車両ではありますが新たな投票所がふえることから公職選挙法による告示が必要となります。また、実施するには最低でも10人乗り以上の広さの車両が必要となるほか、投票前の名簿対照や投票用紙交付などを行うため、車両の横にテントを設置して対応しているケースが多いようです。このほかにも、悪天候時や冬季間の暖房対策、車両の乗降時での配慮が必要であり、さらに事務従事者職員や投票立会人をふやすことになるなど、現状においても苦悩している人的確保が課題であると考えています。
選挙管理委員会としては、あらゆる有権者の選挙機会の確保と負担軽減により、投票率の向上につながることは理解している一方で、これから投票環境の整備には課題も多く、ほかの自治体の今後の取組状況などを見据えながら、本町における導入の可否について検討、判断していきたいと考えております。
2.部活動地域移行の広域化について
質問(片山) 現在、池田町は単独で部活動地域移行の取組を進められておりますが、近隣市町村との広域化が必要であると考えております。池田町が率先して他町村との連携を進め部活の体制を整える考えはございますでしょうか。と申しますのは、高齢化の進行や将来の人口推計から、池田町単独で子供たちが様々な活動ができるという環境を整えるのは非常に困難です。また、広域化の取組となりますと実行までに相当の時間を要するものと思いますので、今からの準備が必要であると考えております。
教育長の所見を伺います。
答弁(教育長) 学校部活動の地域移行の広域化についてでありますが、教育委員会では少子化が進展する中、学校における働き方改革と相まって学校部活動を従前と同様の体制で運営していくことは難しいとの認識のもと、昨年度、池田町学校部活動地域移行検討協議会を設置し、国のガイドライン等をしんしゃくしながら、移行後の地域クラブ活動の実施体制や指導者の確保、広域化などについて協議を重ねております。
こうした中、今年度から陸上競技の地域クラブ活動として、IKEDA TRACK CLUBが創設されるとともに、本町単独での部活動が困難で他町の学校を拠点とする合同部活動につきましては、活動場所までの移動支援に取り組んでいるところであります。また、持続可能な地域クラブ活動としていくためには、何よりも指導者の確保が不可欠でありますことから、広く町民の皆さんに学校部活動の状況や池田町指導者バンクの設置を周知するほか、地域移行の広域化につきましては、当教育委員会から要請し近隣町との協議を開始をしております。
今後、教育委員会といたしましては、検討協議会での議論を踏まえつつ、引き続き地域人材の確保や学校部活動の合同実施に取り組むとともに、近隣町などとの広域化につきましては、主体となる教育委員会の体制や財源、指導者の確保、移動手段等の様々な課題はあるものの、先進事例なども参考にしながら検討を進めるなど、本町の子供たちに体験格差が生じないよう、スポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことのできる機会の確保に努めてまいりたいと考えております。
再質問(片山) 既に近隣町との協議を開始しているということですが、この近隣町との協議とはどの範囲の幾つぐらいの町と進められているでしょうか。またこの協議は現時点でどれぐらい進んでいるでしょうか。
再答弁(教育長) 近隣町との協議に関してでございますけれども、近隣町につきましては池田町も含めまして4つの町と協議を今しているところでございます。その協議の中身につきましては、学校部活動の地域移行に関する課題なども含めた情報交換を行うとともに、現在実施されている合同部活動地域移行させるに当たっての情報共有をまずは図ったところでございます。それぞれの町におきましては、広域的な地域クラブ活動とした場合の実施主体となる体制のほか、合同部活動に伴う移動手段の財源確保が難しい中で、広域化に伴う財源が確保できるか、広域化して指導者の確保ができるかなどの課題が挙げられたところでございます。いずれにいたしましても、今後とも協議を継続していきたいとこのように考えております。
再質問(片山) 既に話が進められていて今は情報共有の段階ということですが、この後話がどんどん進んでいって、まずは4町での取組に着手するところを目指していくと思うのですが、ずっと情報共有で終わってしまってはなかなか厳しい状況かと思うのですが、現在の町で行っている地域移行化については、確か3年間、去年から始まって今年、来年の3年間で行うことが国から示されてたと思いますが、この広域化の取組についても同じようなイメージで進め、できるならそれで進めていきたいのか、もうちょっと時間を要して、そこでこのぐらいの時期にそういった広域化の取組ができればいいといった、そういったお考えはございますでしょうか。
再答弁(教育長) まず、広域化の期間ということですけれども、国のガイドラインで示されておりますのは、部活動の地域移行につきましては7年度までという一定の期間が示されておりますけれども、今改めてスポーツ庁のほうでの案の段階ではその期間がまた延長されると、そういった案も示されております。これはまた具体的にスポーツ庁のほうからその期間の延長については出てくるんではないかというふうに考えております。いずれにしましても、部活動の地域移行と、それから地域移行の広域化につきましては関連する町と協議を重ねながらですね、その広域化がその期間の内で図られていくかどうか十分協議を重ねていきたいとこのように考えております。以上でございます。
3.池田高等学校支援で学級減後の善後策について
質問(片山) 来年度に学級が1学級減少して1学級での募集ということが決まった池田高校につきまして、今後予想されるのは職員数の減少です。これに対応して池田町として何らかの人的な支援を行う考えはあるでしょうか。何らかのと申しますは、例えばまずは事務職員、もしくは先生方の事務を担う事務の支援をする方とか、先生方の授業に入ってサポートする先生といったものを、今中学校でもそのような方はいらっしゃるかと思いますが、これによって教職員の負担の軽減をまずは行うことで、高校での教育環境の維持向上といったところに池田町としてのサポートも可能ですし、また総合学科の特色を活かしたこの専門教科を学べる環境というのは様々な方の、町内外の専門的な知識・技能のある方の支援というものがあることで向上されるものです。これが職員が減っていくことで維持することは困難な状況が想定されますので、こちら池田町としての支援で何とかできないものかと考えております。
町長の所見を伺います。
答弁(町長) 北海道池田高等学校、以下、池田高校としますが、の募集定員は少子化の影響などもあり平成18年度には3学級、平成24年度には2学級へと減少してきました。その後も入学者数が定員に満たない状況が続き、令和4年度からは3年連続で入学者数が1学級定員を下回る結果となりました。近年行っている北海道教育委員会への公立高等学校配置計画に対する要望では、池田高校の募集定員2学級の維持を求めるとともに、総合学科として特色ある学校教育活動の展開に向け、相応の学校規模、教員数を確保する必要があるとし、総合学校設置校1学級当たりの定員引き下げの検討を求めてきました。しかし、本年9月3日北海道教育委員会が公表した公立高等学校配置計画において、令和7年度の池田高校募集定員は1学級と決定されるに至りました。教職員数は、校長、教頭、養護教諭、事務職員、学校医などを除く教諭数として令和4年度の20人から令和5年度は17人、令和6年度は13人と大きく減少していますが、本年度については10名を超える会計年度任用職員により、専門知識を有する民間講師としての授業も行われています。また、今年度からは町で任用した地域おこし協力隊2名を高校魅力化推進員として池田高校に配置しています。業務として、地域みらい留学・北海道外からの生徒募集、探求授業その他総合学科の特色を生かしたキャリア教育の推進、広報活動その他学校魅力化の取組などとしていますが、協力隊員として他の地域から着任した感性や視点を存分に活かし、生徒に寄り添い、地域と学校をつなぐ役割を果たすべく活動しています。高校魅力化推進員の存在は高校の魅力化のみならず、教職員を補助・補佐し、業務負担を軽減することにもつながっているとお聞きしています。池田高校は、北海道立の学校ではありますが、町に高等学校があることの意義や地域活性化に果たす役割・重要性を再認識し、今後も引き続き、池田高校の生徒確保に向けた活動などを続けるとともに、教職員の業務負担の軽減にもつながる支援に努めてまいります。
再質問(片山) 高校魅力化推進員の方が、こちら教職員の補助・補佐により業務負担の軽減にもつながってるという御答弁でしたが、高校魅力化推進員の本来の業務は教職員の事務負担の軽減というよりは地域と学校をつなぐ、もしくは、その魅力を発信することかと思います。ですので、魅力化推進員の方にはそういったところで現在 みらい留学では全国にこの池田高校の魅力を発信できるということも可能な状況になっており、また、今積極的にウェブサイト等での池田高校を更新といったものも確認しております。そういったところに注力していただいて、今回の何らかの人的な支援のところは、やはり純粋に先生方の業務を補助する人といったところと、支援ということが考えられないだろうかというところでして、その点について町長いかがでしょうか。
再答弁(町長) 先ほど答弁しましたように、高校魅力化推進員が自らの本来の業務に携わり、それが地域みらい留学等の推進による生徒確保であったり、また探求授業等のキャリア教育の推進、そして広報活動ということを主とする業務として行っているわけでありますが、通常、これらの業務については池田高校の先生方の業務でもありますんで、結果としてそこの業務に高校魅力化推進員が関わることによって先生方がその他の業務にですね、注力できるという意味で、どちらかというと間接的に議員御指摘の業務負担の軽減になっているというところは事実であるというふうに思ってます。一方で池田高校の本来のと申しますか、学校運営に関わる事務や、また授業を行っていくというところで言いますと、池田高校そもそも北海道立の高校でありまして、先ほど答弁させていただいたようにいわゆる通常の教諭、常勤の先生方が減少していく中で、いわゆる非常勤となる会計年度任用職員での職員の配置を行ってですね、学校運営に当たっているというところで、やはり基本としては道の設置している学校でありますので、道のほうでその施策がとられていくというべきものであって、学校としてもそのように考えているものと自分としては把握をしています。つきましては、そういった形で直接的に町が高校魅力化推進員のようにですね、人的な支援を直接的に行うもの、また行うべきものではないというふうに判断をしておりまして、先ほど言いました高校魅力化、生徒確保という町として積極的に行う部分をさらに推進をしていくことで、結果的に議員が懸念されているような先生方の負担軽減にもつながるのが望ましいと考えているところであります。
再質問(片山) 町長おっしゃるとおりだと思いますのでちょっと踏み込み過ぎました。外部講師の方々が授業に入られるということで、外部講師が出されているということで、こちらについては道の予算もあると思いますが、池田町からも幾らかの活動用の予算というものが出ていたかと思います。こちらは十分な状況にあるでしょうか。
再答弁(町長) 非常勤のいわゆる会計年度任用職員という立場で、池田高校総合学科としての多様な選択科目の 実施が行われていて、このことはこれまでも行われていたことであって今先生の教諭数の減少とは別にですね、かなり多くの先生が在籍していたときから多様な科目を実施していく上で、必要不可欠ということでですね、そういう非常勤の先生方っての配置されていたというふうに認識しておりますし、そこはあくまでも今の制度で言う会計年度任用職員で道の任用でありますので、そのことに対してですね、町が費用負担をしたりということではないんだというふうに思ってます。ただいま探究授業の一部の中で行われているところに対しては、森林木材の活用の授業等に対してですね、町のほうでも総合学科のそういった教育の支援という形では支出させていただいてるところはありますけれども、学校の通常の授業の科目の中での支援ということではないというふうに思います。いずれしても今後ですね、池田高校がやはり総合学科としての多様な選択科目が行えるというところはまさに強みでありますので、そこに対する支援というのは今後もしっかりと池田町としても対応していきたいというふうに考えております。
4.地域おこし協力隊予算の柔軟化について
質問(片山) 地域おこし協力隊予算の柔軟化についてです。現在の地域おこし協力隊の予算についてですが、こちら柔軟化をすることで町外からの魅力の向上、また、協力隊の方がより活動しやすい環境整備、地域への円滑な定住・定着といったことが進められるかと考えております。備品を含めて活動費をより柔軟に活用できる運用であったり、地域に定着する際は、活動期間中に取得した全てのものを貸与、あるいは所有権の譲渡によってそのまま使用できるといったことができれば、地域おこし協力隊の方が池田で3年間活動してそのまま定着するといった見通しを持った活動もしやすくなり、それがまたそういったことができる町ということで町外からの地域おこし協力隊として来てくれるその魅力というものが向上できるかと考えます。こちらについて町長の所見を伺います。
答弁(町長) 地域おこし協力隊、以下、協力隊は、人口減少や高齢化などの進行が著しい地方において、都市地域からの人材を積極的に誘致し、定住・定着を図る取組として、平成21年度に開始され、令和5年度は1164の自治体で7200人がそれぞれの地域で活動しています。受け入れる自治体としても協力隊は斬新な視点を持ちながら様々な地域協力活動を行うことで、地域の活性化に貢献し任期終了後においてもその地域の担い手として定住・定着につながるという効果が期待できます。本町では、平成27年4月に最初の協力隊が着任してから令和5年度末までに14人が退任していますが、退任後本町にそのまま居住している人が10人で定住率は71.4%となっています。また、令和6年度現在は任用型の協力隊6名と、委託型の協力隊3名の計9名が業務に当たっています。
協力隊の活動に要する経費については、国から1人当たり年間520万円を上限に特別交付税措置されることから、本町ではその交付税の範囲の中で制度上決められた報償費と活動費に割り当て予算の各費目に計上しています。予算の柔軟化についてですが、予算は地方自治法に基づき目的に従い各費目に区分し執行することになりますが、現行の区分での執行が難しい場合はその活動内容に合わせて予算の範囲内で流用で対応しているほか、場合によっては補正予算で組み直すなどの対応を行っています。自治体は総計予算主義であるため、多少時間を要する場合がありますが、可能な範囲で柔軟に対応しているものと考えております。
次に、協力隊の活動期間中に取得した備品の貸与、所有権の譲渡についてですが、活動期間中に取得した備品を任期終了後に譲渡することは、備品は町に帰属する資産であることから協力隊だったという理由であったとしても、特定の個人に譲渡することは公平公正な視点で考えると難しいと判断しています。貸与については物品の種類にもよりますが、他の自治体では任期終了後も継続して居住し、同様の活動を行う場合は認めている事例もあるので、情報を収集し検討していきたいと考えます。
再質問(片山) 地域おこし協力隊の制度は相当に自由度の高い制度です。そして自由度の高い制度の中で、3年間の任期の中で起業準備もすることができ、この3年間の期間というのは大変見方によっては長く、そしてここで培ってきた資産、人とのつながりといったものは仮に年間20万円とか30万円の活動予算、これが3年続けられて60万、90万といったものであってもこれは額面以上の資産になる大きなものです。これらをもって池田町に根付くといったものが、これ円滑に進められればすごく起業をするといった面でもしやすい状況になります。また、これらがもう1回買い直さなければならないとかなった場合にはですねやはり根づこうと思ってもなかなか大変な労力が必要になってきます。こういった流れをですね池田町の地域おこし協力隊の設置要綱というものがありますが、例えばそちらのほうに、地域に定着するときにはこういった備品をこのように扱いますといったものが明記することができれば、町外にもこういった3年間まず池田町に来て、人とのつながりをつくって、そして備品設備を用意して、それらをもって地域に定着できますと、見通しを持った活動ができるものかと思います。こういったところで地域おこし協力隊の設置要綱のところからこの大きな流れとして、そういったものを町の考え方というものを整える、明記するといったことは必要ではないかと思うのですが、町長いかがでしょうか。
再答弁(町長) まず地域おこし協力隊にはですね、報償費に関わる分以外にも活動費ということで、そこの中でも自由裁量での活動費が一定程度認められていて、その中で備品購入というところもあり得るんだというふうに思います。一方で活動費の使途ということを考えますと備品購入もその一つなのかもしれませんが、卒業後の起業ですとか定住に向けたための準備というふうに、議員もおっしゃられたように例えば資格の取得をすることであるとか、自己研さんのスキルアップのための研修会参加というようなところも含めてですね、そういった意味での自由裁量の予算をですね活用いただけるのが望ましいのではないかなというふうに考えているところであります。
自由裁量のところの先ほど予算の総額のお話も答弁でさせていただきましたが、そこから補償や義務的な経費を除くと決してそう大きくないものですから、そこを有効に活用いただくという意味ではですね、今言ったような部分にもその予算を利用いただければというふうに思っています。あと、そのほかにですね地域おこし協力隊の起業支援補助金の制度もありますし、また退任後起業等を進める場合には、産業活性化補助金等もありますんでそういったところがですね、もし備品を購入するということであればそういったものも十分に活用いただければというふうに思ってます。あと設置要綱などで明記することである意味何ていうんですかね特別な対応をするということもあるのではないかという御指摘だというふうに思いますけれども、もちろん先ほど言いましたように、流用することだったり予算のですね、補正をするという今の制度の中でできる、柔軟性ということは対応しているというふうに考えてますが、やはりそこは町費・公費でありますので、町の職員、通常職員がですね、予算を執行するのと同じようにやっぱりそこはしっかりと柔軟性を求めながらも、やっぱりその町費、公費を執行するという責任感も持って対応いただきたいという思いもあります。
そういった中で答弁もさせていただいているように、譲渡等については課題が現時点では多いのかなというふうに思いますが、貸与等については先ほど答弁させていただいたように少し他の町村の事例も含めてですね、検討できればというふうに思っております。以上、答弁とさせていただきます。
再質問(片山) 今後、池田町はもう確実に人口が減少していき働く人も減っていくという状況が明らかな状況で、これから、今までも度々言ってきましたが、新たな人が外から来て事業を起こしてくれるといったことはもうなかなか期待、また事業が来てくれるというのを期待するのは難しいのではないかと思います。と、したら町は縮小していく一方になってしまいますが、ですがこの地域おこし協力隊っていうのはそれを解決できる可能性のある強力な制度であると思います。まず何をするにもお金がかかるということですので、お金のかかるところについて可能な限り地域おこし協力隊の方が伸び伸びと活動して、最終的な見通しを持って活動しないと自分1年後どうなるんだろう、2年後どうなるんだろうって不安の中で活動するのは、やっぱりこの立場としてはつらいことかと思いますので、その先を見通せる形、そしてできれば100%定着してもらえる町であるといったことを目指していくべきであると思います。といったところでこの予算の柔軟化というところは非常に重要なものだと思って質問をしております。この予算、お金の使い方とか購入とかといったところで重要だと考えているのですが、町長はその点いかがお考えでしょうか。
再答弁(町長) 今の、いわゆる予算のですね対応というものが自分自身としては流用 であるとか、補正予算が必要というところはですね、一般論として少し形式的だというふうに受けられるところもあろうかというふうに思いますが、先ほど述べましたように公費、町費を使って物事を進めるという上では、最低限のですねルールにのっとって行っているという認識で、そのことが事業を行っていく上でのですね、大きな足かせになってるのかというと決してそうではないんではないかなというふうに自分自身では受け止めています。ただ議員御指摘のように本当に伸び伸びと、また先を見通せる環境で活動いただくってことは本当に重要であるというふうに思ってますし、単なる原則として1年、最大3年という任期だけの期間だけではなく、その後も含めてですね、しっかりとした活動を行えるということは、もちろん周り、町としても大きな責務を担っているんだと私は認識をしているところでありますが、そのことについては先ほど、あと予算のところの備品の購入等のところに話が戻るとするとですね、やっぱりそこは他の制度も十分に活用できる環境でありますし、そういった先を見通すからこそ、その時のためのスキルアップや資格取得も含めた自由裁量のですね、予算を有効に活用いただきたいという考えにあります。
○議長(丹羽泰彦) 片山議員よろしいですか。それでは一般質問を続けます。