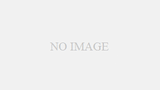一般質問
9月定例会では一般質問を2点予定しています。
1.奨学金返済に対する助成金の創設について
質問(片山) 現在、道内各地で高等学校や大学への進学の際に借り入れた奨学金の返還支援を行うという取組が広がっている。池田町は、就職等により地域に定着する人材の確保、それから少子高齢化による人材不足への対応といったところで課題がある。そして、池田町は平均的な所得がそれほど高くないというのが現状であるので、奨学金を返還しなければならないといった将来の不安の解消といったところも考え、池田町として奨学金の返還支援というものを行うべきである。
こちらの返還支援については、国の特別交付税の措置の対象であり、現状であれば1/2が措置対象である。特別交付税の対象要件の1つに、各町で設定される総合戦略で若者定着に向けた奨学金返済支援事業というものが明記されている必要がある。池田町のまち・ひと・しごと創生総合戦略(R3.3.31改正)のp.76基本目標2、移住・定住対策の推進の主な施策、具体的な事業に「若者定着に向けた奨学金返済支援事業」がはっきりと明記されている。
答弁(町長) UIJターンや地方就職など若者の地方定着のため、地方公共団体が奨学金の返還を支援する取り組みが全国各地で行われている。本町では池田町まち・ひと・しごと創生総合戦略、基本目標移住・定住対策の推進の具体的な事業として、若者定着に向けた奨学金返済支援事業を登載しているが、現時点では実施に至っていない状況である。
北海道ホームページ道内市町村における奨学金返還支援の取組では、道内52市町村の支援制度が紹介されている。支援の方法は、自らが借り受けた奨学金の返済額について全部または一部を補助するもの、町が貸し付けた奨学金の返済額について全部または一部を免除するもの、就業先企業へ補助するものなどとなっている。なお、要件として所得の制限を設けるもの、居住市町村内の就業に限定するものなどがあり、補助や免除の期間も短いもので数年、長いもので全返済期間など様々となっている。また、これら以外にも、医療や福祉など特定の業種や職種の人材確保を目的とした奨学金返還支援も多く取り組まれている。国でも地方からの人口流出への対策としては、若者の地方定着の取組がとりわけ重要とし、奨学金を活用した若者の地方定着促進に係る特別交付税措置を行うなど、就職などにより地域に定着する人材を確保するための施策を講じている状況にある。
議員質問の高等学校や大学などへの進学の際に借り入れた奨学金返済に対する助成金の創設につきましては、就職などにより地域に定着する人材の確保や人材不足の対応、奨学金返済に係る将来への不安解消を図るため、その実施に向け、具体的な検討を行う必要があると考えている。奨学金制度の趣旨、国の施策の考え方などを踏まえるとともに、公平性の確保、地域経済への効果なども考慮し実施方法の検討を進めることとする。
再質問(片山) 他町村の取組から介護とか看護とか特定のこの職種に対する返還といったものも多くあるが、これは池田町は取り急ぎ取組が必要なものではないかなと考えている。ただ一方で、就職等により地域に定着する人材の確保といったところでも、池田町はなかなか働く場所がないという声も多くあり、例えば一定の基準を設けて町に登録した事業者にその返還の支援を行うといった取組をしている自治体もあるので、できるだけ広く多くの方に使っていただける、将来池田町で働いていくっていう姿が若いうちから描ける、それは御家庭のほうでも、そうであれば池田町に子供を送り出して、そのまま外で働いてきて戻ってきて、働き手となる、町で生きていくといったことが描けるというような、そういった姿が描ければ良いと考える。
今の町長のこの答弁の中で、どういった範囲でこの奨学金の返済を介護、看護に絞るのか、もっと広げていくのか、どのぐらいの広さで考えているかが不明だったので、この部分について町長の所見を伺う。
再答弁(町長) 奨学金返済に対する助成・支援で、どの範囲でどのようにというところについては、まさに検討していかなくてはならないところである。議員指摘のように、この制度そのものをまず若者の地方定着、2つ目に人材不足への対応、そして3点目に奨学金返還の不安解消というそれぞれの目的を考えたときに望ましい手法が、それぞれに若干違いがあるのではないか、どこを優先させていくというように自分自身考えているところである。
奨学金の返還の不安解消ということであれば、まさに返還に対する支援というところになろうかと思うが、既に道内で多く取り組んでいる自治体で、制度はあっても活用の範囲がそう進んでいない事例も多いように伺っており、そもそも若者の地方定着や人材不足というところへの対応であれば、またそこを奨学金というところに強く限定をするか、しないかというところも含めて検討する必要があるのではないか。
一方で先ほど片山議員からは福祉とか医療とかのいわゆる資格職の部分については必要性が、比較論議であろうかというふうに、現状の福祉現場などを考えると、どうしても有資格者が就労していかなくてはならないところで、その人材確保っていうのは実は私としては特に町の中での労働力不足の中でも急務ではないのかと、そういった資格取得に対するところの支援であればまた、そこでどういうものを進めるべきかというところも改めて論議をして、そういった意味で幅広い観点から、若者の地方定住、人材不足といったところをしっかり対応できる制度、その中で奨学金返還の不安解消というところも含め検討した中で、いずれの方法かをしっかり精査した中で進めていくべきものであると考えている。
2.重層的支援体制の事業について町の取組
質問(片山) 令和2年に社会福祉法が改正され、重層的支援体制整備事業が創設された。社会福祉法の趣旨としては、最終的には地域共生社会の実現というところを目指したものではあるが、この法の趣旨に則り池田町として、複数の係を横断し支援を必要とする人に対する包括的な支援体制の構築といった点で、また重層的支援体制整備事業については国の財政措置があります。既に十勝管内でも幾つかの町村で行われており、全道的、全国的にもその取組事例というものがある。こういったものを活用することで、池田町としてこの重層的に支援を行う、重層的支援体制整備事業というものが進めやすい状況にあるから、池田町としてこの重層的支援体制整備事業を進めていくべきである。町長の所見を伺う。
答弁(町長) 今日の社会は少子高齢化や人口減少、地域社会の脆弱化など、社会構造が変化するなか、人々が様々な生活課題を抱えながらも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民等が支え合い、一人一人の暮らしと生きがいをともに創っていくことのできる地域共生社会の実現が求められている。しかし、実現に向け取組を進めるうえで、地域住民等が介護・障害・生活困窮など複数の課題を抱えるケースも多く対応に苦慮することから、令和2年に社会福祉法が改正され、対象者の属性を問わず相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的・包括的に進める体制づくりとして重層的支援体制整備事業が創設されたと承知している。
当該事業については、実施を希望する市町村が申請する任意事業となっており、十勝管内では令和6年度で6町が実施している。本町では当該事業には取り組んでいないものの、複数の課題を抱えた相談に対応するために、関連する部署が横断的に連携することが最も重要であることから、令和4年4月に保健センター内に総合相談窓口りんくを設置し、子育て、保健、生活困窮・障害、高齢者・介護に関する事案に対し、保健センター内の関連部署が連携し、支援の必要性や具体的な方法について外部の関係機関とも調整を図りながら対象者の課題解決に向け一体的・包括的に取り組んでいる。
また、財政的措置の活用としては、当該事業を実施した場合、新たに人材育成やコーディネーターの配置等に関する補助を受けることができるが、一方で実施計画の策定や各部署を横断した事務処理など事務的負担の増加が見込まれる。さらに、事業全体を円滑に進めるためには調整役が必要となるが、高い知識や経験を有した人材確保が難しいといった課題があり、こうしたことから、現時点においては財政措置の活用含めた当該事業の実施には至っていない。
取組事例の活用に関しては、他市町村を参考にしながら当該事業で定められた総合的な相談支援体制整備や必要とするサービスを相談者へ繋げる参加支援、関係機関との連携のほか、池田町社会福祉協議会が実施するサロン事業の通いの場やボランティア活動の支援等も充実させ、地域の中で包括的に支援を進めるために必要な体制を整備している。今後においては、重層的な支援体制の重要性も認識していることから、本町の既存の相談支援等の取り組みを生かしながら、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築に向け、重層的支援体制整備事業の導入も検討していきたい。
再質問(片山) 再質問が2点ある。福祉に関わる窓口は現在7か所の窓口があってわかりにくい。例えば重層的支援体制整備事業で、インターネットで検索すると上から出てきた資料の場合ですが、例えば全体の枠組みとしては、このように支援します。というものが、はっきりと明示されている。重層的支援体制整備事業を行うと、「この枠組みの中で福祉として支援する。それは池田町の役場だけではなくて、ほかの事業者とも連携をして行う。」といったところを明示できる。ここは良い点である。
現状であれば包括的な相談事業(係を横断した課内での連携)といった点で町としては整備されているんだろうなと思います。ただこの重層的支援事業につきましては、多機関協働事業、アウトリーチを通した継続的支援事業、参加支援事業、地域づくり事業もあり、町全体で支援をする。福祉の担当課の中では対応できない、間に落ちてしまった問題、福祉課ではそもそも対応できない問題、例えば経済… 働く場所とか他の課との連携といったところでも全体的な支援が必要である。
支援体制を町民の方々に伝えるといった取組についての考えが1点目の質問。それから2点目、先ほどの多機関協働事業、アウトリーチを生かした継続的な支援事業といった、他の事業者との連携といったところで、重層的支援事業を行わないにしても、やはりこういったものをしていく必要があると考えるので、そういった取組をこれからまずは進めていくに、具体的な考えはあるか。この2点について伺う。
再答弁(町長) 議員も指摘のように、本町が行政内での相談支援に分野を超えて、包括的に対応しているという意味では、1つ目の一番重要な相談支援というところは、まさにこの重層的支援体制整備事業と同じ形の考えの中で行われていると考えている。
一方で、そのほかに支援を要する人の参加支援であるとか、地域づくりに向けた支援というものが必要になってくるものであり、例えば参加支援等については、ニーズを踏まえて丁寧なマッチングをすることやメニューづくりをすること、また、その当事者だけでなく、受け入れ側の組織等への支援もするというように行うものもあり、今、地域づくりに向けた支援ということでは、議員指摘のアウトリーチ等を通じた継続的な支援事業や多機関協働事業というところにつながっていく、ある意味本当に重層的支援体制っていうのは、個別の支援を包括的に行う、相談に対応するだけではなくて、本当町を挙げての包括的な支援体制の構築というところである。
もちろん本町においてもこの事業での該当で実施しているわけではないが、地域の様々な関連する機関とも協働しながら、様々な活動を務めており、一定程度の地域活動があるのは事実であるというように思うが、様々な伴走支援を系統立てて実施しているというまでは言えないところも多々あろうと考えている。
そういった点から重層的支援体制の実施、もちろん最初に実施計画を立て、さらに様々な重層的支援の支援会議を立ち上げて協働していくというような意味では、様々な検討をしてこれから取り組んでいかねばならない制度であるというのがまずベースにあり、議員指摘のように、そこを進めることで、いろいろなことが住民の皆さんに伝わっていくというところで私もまさにそのような考えがあるので、答弁の最後にしたように、やはり近い将来この事業を本町としても取り組んでいく。他の自治体の事例が、本町と同じような事例で、行政的な相談支援のところができていることをもってスタートして、その制度の財政的な支援を受けながら人材育成などを図っているという実態もあるのではないかと考えており、制度活用を前提とした、取組が今後必要になってくるだろう考えている。
一方で、ただ今行っていることを生かして行うだけではなくて、いろいろと前段に整理すべきものが多々あるので、そういったところをしっかり整理した上で進めていく必要があると考えている。
再質問(片山) 町の方々にこういった体制で支援しますよといったものを伝えるといったところについて、重層的支援事業体制のそのままでなくて良いが、「このようい支援する」「こういった連携とっている」といいうところを明示することについての考えは。
再答弁(町長) 最初に答弁をしたように池田町では「家族まるごと相談窓口りんく」といった窓口を設け、そのことについても周知をしているところであるが、実態からするとですね、そういった周知によって全体的な複数の支援を要することを相談を受けるよりも、直接当事者にとっては一番課題となっている支援の相談に訪れて、その支援をしていく中で、ほかの課題も実は有しているんだということが明らかになっていく場合が多いと把握している。もちろんそういった意味では複数の課題について相談を受けるという体制を現在も行政の中ではとっており、その次の地域としての支援のところまでの周知に至ってるかというと、当該事業の流れまでにはなっていないと思っているが、一番最初の入り口のところでは支援での周知も行っているので、それが議員指摘のように当該事業を該当させることによって、住民の皆さん、支援を要する人たちにこういったことを行っているんだということもですね、よりわかりやすくなるということも一つの効果だ認識をして今後検討を進めていく必要があるというふうに思っている。