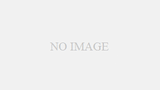令和6年6月定例会についての投稿です。
一般質問
1.修学旅行費用補助について
質問(片山) 所得にかかわらず、義務的な費用として発生する小・中学校の宿泊研修や、修学旅行費の負担は大きい状況である。また、物価高騰が続く中、学校としても修学旅行にかかる費用を抑える努力をしているとは思うが、その結果学習指導要領に定められる修学旅行等の本来の目的も達成が困難な状況ではないか。これらの費用を町として補助することで、子育て家庭の費用負担を軽減し、義務教育の円滑な運営を図るべきである。
答弁(教育長) 実施に要する費用の補助等に関しては、管内の7町において予算措置されている。修学旅行につきましては、燃料費等の物価高騰による交通費や宿泊代などの値上がりに伴い、必要経費の増加とともに、保護者負担額も増えていると承知をしているが、仮に子育て家庭への費用負担軽減として、修学旅行費用の半額を補助した場合、単年度で約150万円の財源が必要となり、これらは将来にわたり措置が必要な経費となることが見込まれる。教育委員会としては、義務教育段階における効果的な学校教育活動や保護者負担軽減の観点から、修学旅行費用の補助に向けた検討の必要性は認識をしているが、限られた財源の中で持続可能な地域づくりに向けた子育て家庭への支援策については、町全体で総合的に判断されるべきものと考えている。
再質問(片山) 財源として池田町こども夢基金の活用が十分に可能である。来年度にむけて小学生は3万円ほど、中学生は7万円程の費用が積立てられている。実際には他にも修学旅行にかかわり、子供たちに渡す道具、宿泊のための用具、当日の小遣いなどを加味すると御家庭の負担が大変大きい状態である。帯広市では費用負担軽減のために宿泊旅行の日数が削減された。幕別町では費用負担軽減と子育て環境の向上を目指して、半額の補助を開始したとの報道があった。池田町は財源があり、有識者でつくられる人口戦略会議では消滅可能性自治体とされている。財源があり、そのような未来が予見されている状況であり、全ての児童生徒とその御家庭の負担に関わるものであるから、修学旅行費用の補助については大変必要性の高いものである。
答弁(教育長) 財源としての子供夢基金の活用といったような趣旨であったかと考える。子供ゆめ基金に関しては、約8億円程度と認識をしているが、基金をどのように活用するかについては、教育委員会としては所管外である。個人的な意見・考え方ではあるが、子供ゆめ基金の財源についてはふるさと納税からの積立てなどとなっており、大都市圏の税収の減少などの課題もあり、将来にわたり保障された財源ではないとの認識を持っている。また、現在の基金残高につきましては、今後に何かしらの恒久的な事業の推進が必要となった場合、決して潤沢な財源とは言えないのではないかとも考えている。将来を見通した基金の活用が大変重要であると意識をしている。修学旅行費用補助の検討の必要性は十分に認識している。
再質問(片山) 池田町こども夢基金の活用にはこだわっていないが、短期的には池田町こども夢基金を使ったとしても良い。将来的に子供たちを育てる環境、特に全ての子供や御家庭に関わってくるものがこの修学旅行ですので、将来的には一般財源を充てていくということも十分に考えてよいものである。それぐらい、必要性の高い支援、補助ではないだろうかと考えている。必要性は認識しているということだが、かなり重要度が高いものだと考えているのですが、その重要度の部分については。
答弁(教育長) 修学旅行費用の補助金の検討にも、その必要性につきましては、私としては十分に認識をしている。教育委員会には予算編成権がないので、町全体の予算の中で、特に子育て支援、子育て家庭への支援策という、広義の意味では、その中で議論されるべきものとこのように認識をしている。
2.子育て家庭への支援策について
質問(片山) 生活環境は昔と比べようもなく、よくなってきている。良い環境の中、経済面で子育てがしやすい町づくりを進めるために、子育て世帯向支援の充実が必要である。今であれば生活には困らないためのものは揃っているので、規模は縮小したとしても、高齢の方が町にいて、目のあるところに、ちっちゃいお子さん、親御さんがいて、その中、小中学生が走り回ってて、高校生がいて、働く世代の人が暮らしていてお互いに助け合って、支え合って暮らしていけるような町づくりも、実現できると考えている。この町に子供の姿という存在は不可欠なものである。例えば、子育て世帯に対する夏の電気代や、冬の灯油代(灯油代相当の電気代)の支援。これは子育てをするに当たって全ての人が関わるもので、有効であると考える。このような町独自の支援をさらに充実していく考えはあるか。
答弁(町長) 池田町第5次総合計画における基本目標の2、心と体を育てる、健やかに暮らせるまちを目指してを具現化するため、子育て環境の充実は極めて重要な政策であると認識している。過去に新型コロナ対応や、物価高騰対策として、国の交付金を活用した臨時的な生活支援を実施した経過もあるが、議員指摘の子育て世帯向けの支援の充実として、夏の電気代や冬の灯油代等の支援を行うことなど、子育て世帯に特化した恒常的な生活支援につきましては、町民全体との公平性の観点から、現時点では考えていない。
再質問(片山) 国は子育て支援に関わり、今年度莫大な予算を計上している。北海道も子育て世帯の負担軽減というものを行っている。町民全体との公平性との観点から現時点では考えていないとのことだが、子育てをするにはお金が非常にかかるものであって、この「子育てに関して特別に発生する費用を支援する」ことによって、町全体で子育てに関わる費用を等しく負担して、子育て世帯とそうでない世帯と、経済的に公平な生活環境の中で子供を育てていくといった施策を行っていかないかというものである。例えば今回は、電気代、灯油代の補助等だが、給食費の補助、教育にかかる費用の補助、課外活動に係る費用の補助なども有効であるとは考えるが、子育て世帯に特化した恒常的な支援というのも、国がして、北海道がしているなら、やはり池田町も、何か行っていくのは支援の方法の一つであり、また必要ではないかと考える。
再答弁(町長) 国や道が、子育て世帯に対する支援充実も図られている今日であり、さらにそこに対しての町のさらなる施策ということだが、先ほどの答弁は、子育て世帯に対する経済的な支援策として、いわゆる生活に直結する電気代とか燃料代については、課題があるのではないかというところの見解であり、そもそも子育てしやすい環境を整備するために、経済支援は必要不可欠であるというふうに自分自身も認識をしている。ただ本町が進める、安心して妊娠、出産、子育てできる環境をさらに教育が受けられる環境の充実と言ったこと、また子育てにおいては、伴走支援、一体的に相談訪問、指導等を行う伴走型の支援を主軸として、そこと連動した形の経済的支援がより望ましいであろうということでこれまでも進めてきている。指摘の子育てそのものまた教育に要する、直接的な経済、財政的なものを負担する考え方にあり、これまでも幾つかの施策を講じているところである。一方で電気代灯油代という、生活に要する支援ということも生活支援という言葉で回答するが、もちろん町民全体の公平性というところも課題というふうに思うが、様々な角度から多角的にですね、継続性を持って取り組んでいかなければならず、少子化は短期で解決される課題ではないと考えており、継続性を持って複合的に町として取り組んでいく。そのための財源措置ということも含めた上で、生活支援よりも、直接的な教育、それから子育てに要する費用のほうを中心にですね、支援をしていける形を今後も、現在やってるものがベストではないと思う。不断に見直しを行い、必要な実効性ある施策を今後も展開していきたい。
3.高島地区の防災体制について
質問(片山) 高島地区の防災体制について、前回3月定例会の一般質問の際、避難場を4か所に集約するということだった。高島地区入っていなかったが、高島地区の避難所はどのように考えるか。高島地区に長期の避難場を設置すべきである。池田町北部地域の中心地に立地しており、池田町市街地外に位置拠点の整備をして、北部全域をカバーするといったことをしてよいのではないか。
答弁(町長) 令和6年第1回定例会議での一般質問に対し、今後、冬季の地震災害時に停電が発生した場合を踏まえ、避難場を集約化していく考えがあることを答弁をした。指摘の高島地区は北部地域コミュニティセンター(以下北部コミセン)と旧高島小学校を指定避難所としており、特に北部コミセンは、北部地域の中心地に立地し、地域住民の皆さんもふだんから利用していることから、防災上においても重要な施設であると認識している。また本町における、想定最大震度を示した地震揺れやすさマップのデーターでは、高島地区は、池田利別地区と比較すると、揺れにくい地域となっています。地震災害が発生し、避難場生活を余儀なくされた場合、高齢の方の多い高島市街地においては、震災後のコミュニティーの維持や避難生活後頻繁に自宅に戻って後片づけを行う利便性等も考慮すると、中長期的に北部コミセンを指定避難所に指定することが理想的であることから、今後、北部コミセンにも大型発電機を後づけできる機能を備えるなど、電源確保について検討していく必要があると考えている。なお、水害時の避難体制だが、現在北部地域の水害時の避難場は、ほとんどの校区が旧高島小学校となっている。このうち、高島市街地から旧高島小学校までの距離は2キロ弱と遠く、高齢者等の避難行動、要支援者が徒歩で避難することを想定すると、まず十分から1時間程度を要することとなる。水害時は早期避難が推奨され、避難に要する時間や内水氾濫等による緊急安全確保も含めた避難体制を考慮すると、避難所の見直しも必要であるとの考えから、新たな指定避難所の検討を進めているところである。また、北部地域の避難体制の確保については、早急に解決すべき検討課題の一つとしてとらえており、今年度中に、北部地域でも地震を想定した避難訓練の実施を検討していく。
4.ブドウ・ブドウ酒事業会計の黒字化について
質問(片山) ブドウ・ブドウ酒事業会計は予算の段階で3200万円の赤字を見込んでいる。減価償却費が7800万円計上されているので、キャッシュフローを考えると4600万円の黒字があると見ることも出来て、帳簿上の赤字は問題ないと考えうる。しかし、それはキャッシュフローがプラスの時の話であって、実際はマイナスであり、長期的に見ると現金はどんどん減っていくこととが予想されている。減価償却後に赤字を計上するということは、当初の投資を回収出来ていない状態であるということでもあり、営利を目的としていない公営企業とはいえ、投資分の回収はすべきである。そこで、以下4点について町長の所見を伺う。
1点目、キャッシュフローがプラスになる、事業収益は幾らと考えて経営しているか。
2点目、減価償却後の純利益が黒字になる事業収益は幾らと考えて経営しているか。
3点目、キャッシュフロー、事業の純利益がともに黒字になるための具体的な方策や、取組の方向性をどう考えているか。
4点目、事業収益の増加に向けた広報戦略として具体的な取組は。
答弁(町長) 本町のブドウ・ブドウ酒事業は、内部留保に当たる利益剰余金を蓄え、計画的な投資に努め安定経営を進めてきた。しかし近年では、新型コロナウイルス感染症拡大による、全国的な酒類消費の低迷、加えて本事業においては平成29年度から令和元年度までの3か年度で実施したワイン城改修事業の減価償却費の増額等の影響もあり、平成30年度以降、純損失を計上しているが、無借金で年間の事業収益額に匹敵する現金預金を有した経営を続けている。
まず1点目について、減価償却費から、長期前受金戻入れを控除した額を加えた額の範囲内に、投資活動によるキャッシュフローが収まっていれば、おおむね資金は増加すると考えている。ただし、棚卸資産の増減額を別途考慮する必要があり、近年ブランド製造再開しているので、その分は棚卸資産が増額し、現金が減少していることになる。なお近年のキャッシュフローを見ると、令和元年度ワイン城改修事業を行い、当会計では借入れを一切行わず、前年度末10億円だった現金預金は、当該事業の支出を完了した令和元年度末で7億円に減少し、さらに、コロナによる影響を受け、令和3年度末の現金預金は6億3400万まで減少したが、令和5年度末では6億9500万まで戻ってきている。
次に2点目ついて、令和6年度当初予算をベースに考えると、純損失を3208万6000円計上しているので、計算上収支の損益分岐までは同額程度の増益が必要となる。増収により増額となる、製品費、酒税及び営業費のうち、運搬費など直接販売に直結する経費を加味し、必要増収額は9200万円となる。なお金額はいずれも税抜きとする。これは予算時の営業収益額7億2000万に対して、13%程度増加させることとなり、現在の経営戦略の中長期計画において、7億8500万円の製品売払い収益を見込んでいるので、さらに増額する必要があります。また費用の削減についても取り組んでいくことが重要である。
次に3点目について、多様化する市場ニーズにこたえる製品や、より高品質の製品を効率的に製造し、高収益化を目指している。さらに地域に根差したブドウ品種の確立に努め、個性と地域性にあふれる高品質なワイン製造の体制を確立するとともに、酒類流通形態の特性を生かし、取引先との関係強化による販売体制の推進を図っていく必要がある。また、ワインツーリズム等、池田町の観光振興や他の産業との連携推進によるブランド力強化を図るなど、生産体制、販売体制、経営体制、全ての面から経営の安定化を進めていく必要がある。
最後に4点目について、これまでワインの販売促進に対し効果的な広報活動としては、酒類流通形態の特性を生かし、取引先との関係強化を図ることと連動させ、業界誌など、流通関係者への広報活動や取り先のギフトカタログ、各種ポイントカード等を顧客向け広報活動との連携を基本としてきた。その上でこれまで商品シェアの高い地元にほぼ限定されてきた消費者への直接的広報活動については、SNS等新たな媒体を活用し取り組んでいく。各種コンクール受賞やメディアへの露出が、即効性においては効果的であると考えている。また、本年度はワイン城50周年を迎えているので、50周年記念イベント後も、話題性を一過性とさせることなく、十勝ワインのブランドイメージ浸透戦略としてプロモーション事業を予定している。さらなるワイン文化の振興とワイン消費の回復、向上に向け、町内外に向けて情報発信していく。
再質問(片山) 計画的な投資に努め安定経営を進めてきたというが、これまで何十億円という利益を町に還元してきたと思う。しかし、そのほぼ全てを町に還元して、実際にはブドウ・ブドウ酒事業への投資をしてこなかったのではないか。確かに純利益に対して減価償却費を引いて、投資活動のキャッシュフローが収まっていればキャッシュフローはプラスに本来なってるはずである。今回令和5年度末で6億9500万円まで戻ってきている現金については、実際この投資活動にはキャッシュフローが減少したことによって一時的に増加しているものではないか。昨年8月の所管事務調査においては、設備投資に50%の補助を入れても、なお現金が減少していく予測であった。もし補助が無ければ10年以内で、現金が枯渇して事業の存続が危ぶまれる状況であったと承知している。今、現金が増えてきて戻ってきているということであれば、現状のままの売上でも、6億9000万円前後の現金を推移したまま維持していくもしくは増加していける見込みまで回復したということでよいか。今後は、これぐらいを維持していけるという状態か。
再答弁(町長) 現金が令和元年度までの大型投資にあたるワイン城改修事業を終えて、その後、現金が戻ってきているというのが実態であるが、大きな投資を終えた後のこの数年間であり、当然に次の大型の改修、投資事業等も、計画控えが控えている。今は純損失を計上している中であるが、本来であれば利益を計上し、利益剰余金も一定程度増やしながらということで、残念ながらそこに至っていない状況であるが、少なくともキャッシュについては、増額をして次の大幅な投資に備えるような時期になろうかと考えている。
昨年の所管事務等で現金が今後減っていくというところの計画であるが、令和13年度までの経営戦略の資金計画のベースとして話しており、その大前提が収支的には令和元年度以降、コロナ禍の販売も回復をして、収支が拮抗するところまで令和7年度以降には持っていける。加えて令和4年から13年度の10年間で約7億円の投資を予定している。この中で一般会計にある基金を活用をするということでブドウ・ブドウ酒事業会計的には、事実、影響額は4億円ぐらいの投資金、キャッシュが出ていくことになるが、現状よりも単年度の平均的な投資額が大きい。瓶詰工場のラインの更新や、大型事業も控えている。そういったものを加味すると令和13年度末で3億1000万まで減少するというようなところを見込んでいるが、この金額が事業運営上どうかというと、一般会計から3億の負担を受けることができる前提になっているが、資金運営上は何とかそこにもっていけると思っている。
細かいところになるが、棚卸資産の増減額が当会計の場合に非常に大きな影響を与え、この資金計画上も令和5年度の当初予算の金額がベースになって積み上げられた数字である。そのため決算をすると棚卸資産になるものっていうのはブドウの購入代金であったり、瓶、段ボール等の資材の購入代金であるので、予算不足が絶対に許されない項目であり一定の不用額が出る。そこに不用額が出るということは、結果的に現金はそこまで減らないということになるので、その影響も含めた中で、予算をベースにしているので、現金が少し実態よりも少なくなっているというところではあるが、基本的には、昨年所管事務調査で示している、令和13年度末3億1000万といったところの計画は現時点でも変更なく考えている。
再質問(片山) どのような事業であれ金がなくなってしまっては継続出来ないので、この現金をしっかり維持するということは極めて重要なことである。減少していくことが分かっているのであれば、その手当ては今すぐ何かしなければならないと考えている。減価償却後の純利益は黒字になる事業収益の9200万円(税抜)で13%程度増加させることが必要である、と現在分かっている状況であるのであれば、今までは昨年度の売上高に対して2%ぐらいのプラス3%プラス、そういった形で計上されているのかもしれないが、やはりこれまでの投資分設備投資分の改修もあわせて、この13%の売上げの増加を、まずは最初の目標としなければならないのではないか。
黒字化のために、本来であればコントロールできる固定費の削減を行っていかないと、なかなか厳しいものと考えるが、現在は十分な現預金を持っている状態なので、固定費の削減も頑張りつつ、まだ十分にある資金を使って、目標損益分岐点までまず見定めて、そこに向けて全力で資金を投入して売上げを拡大していく必要がある。目標の設定の仕方について、損益分岐点を目指し、そこに向けて真っすぐに行くという計画を立てては。
再答弁(町長) 損益分岐になるところを目標立てて、そこに向かっていく企業経営ということかと思うが、当然にそのことが必要であり、今回質問されたキャッシュフローの関係とは私自身は、当然にキャッシュがあれば良いというのではなく、当然公営企業といえどもブドウ・ブドウ酒事業は収益的な事業なので、収支が成り立つことが必要不可欠だともちろん考えている。先ほど示した様々な方策を実行することでそれを早期に実現していく必要があり、中長期の経営戦略では当然に損益分岐は、早い段階にそこに達することを前提とする売上げ見込みとして、そこに全力投球をしている。今回の投資については、生産ラインの効率化という計画もあり、当初行うことが将来的な費用削減であったり、経営の健全化に寄与するということも当然考慮していかなくてはならない。一方でこれまでも議会の論議の中でもあったが、投資は当然に一時的には現金が減っていく。さらにその中で、結果的に後年の減価償却という非現金支出でありますけど、負担増ではある。将来的な、利益、企業の経営安定のために、一時的な損失の計上、またそれが減価償却費現金支出の範囲の内であれば、ある程度は恐れなく果敢に攻めていく必要があるということで、これまでワイン城の二回の大きな改修事業や、製造施設への投資等も行って、単年度ではなくある程度長期的な展望に立って必要な投資も行う。その上で、事業経営の安定化を進めていきたい。
再質問(片山) 長期的に、何年後に損益分岐点を超えるという形かとは思うが、できれば来年超えたほうがより安心できるので、いかに短期間で損益分岐点を超えるかといったところを考えて、3年後ぐらいまでに、こればいいなとかではなくて、来年超えるためにはどうするんだろうといったそういった考え方をしないと、なかなかその目標を達成するのは難しいのではないか。実際、認識されていないものは手にとられないので、できるだけ多くの人に知ってもらうといった広報戦略が必要である。そういったときに、広報予算は400万円ぐらいだったと思うので、売上高に対して1%に満たない広報予算をかけて、それがうまく使えてない状態だが、実際広報は非常に難しいもので、うまく使うには専門的な知識や技術が必要であると思う。ブドウ・ブドウ酒事業会計の売上高拡大と利益の確保に向けて、そういった専門的な、広告予算をうまく使って、たくさん売上げを上げてくれる専門家に委託するといったこともまた一つの手であるかと考える。
再答弁(町長) 広報活動は、営業戦略、販売戦略の当然重要な一つのパーツだと考えている。一方で、何を広報して広げていくのかを見据えた広報活動が必要と考えている。一般的に広報と考えると、消費者に対して直接的に戦略を行っていくということがイメージしやすいが、当会計はメーカーなので、酒類流通の形態の特性などを生かして生産者や中間の流通で卸売業、その先の小売業、そしてその先に消費者というものがあり、その販売形態を最優先させて、まずは商品を取り扱う販売に従事する人たちに、私どもの商品をしっかり知っていただくという戦略を基本としてきた。一方で地元はある程度の、例えばしっかりと広報しても、肝腎な商品が取扱いがないところであれば、その効果は発揮されないわけであり、十勝という範囲になると商品のシェアも大きくなり、そこには消費者に直接広報するようなこともこれまで行ってきた。本町の会計の清算規模、そもそも公営であることの企業認知度等を踏まえると、よく売上の5%が広報に使うべきというような論議もあったりするが、本町の特性からすると過大なコストではなく、しっかりとした企業イメージというものを打ち出していくことを優先されるべきと考える。専門家に対する委託について、例えば50周年記念のプロモーション事業はまさにプロポーザルである。提案をいただいた中で、特定の事業者に継続的ということはないが、今回の事業に関して委託をして、その上で提案をいただいて進めていくという方策も取り入れており、通常内部で進めている広報、いわゆる広告代理店等のですね関係の中で進めているところだが、その手法については提案いただいたことも踏まえて今後しっかり検討した中で進めていきたい。
5.池田高校支援のコーディネーターの活用について
質問(片山) 今年度配置された池田高等学校の池田高校魅力化推進に、町として期待する具体的な取組をどのように考えるか。また昨年度は、特に池田高校の魅力を発信する広報面が弱かったと認識している。今年度は解消する見込みにあるか。
答弁(町長) 本町では、北海道池田高等学校(以下、池田高校)の学校活動への支援を目的に、今年度、3名の地域コーディネーターの任用及び配置を計画している。5月1日からは、外部人材制度の活用により、地域おこし協力隊高校魅力化推進員1名が着任し、探求授業へのかかわり、生徒募集に係る広報等の業務を中心に活動している。また、今年度池田高校では、ホームページによる情報発信を強化している。北海道教育委員会による小規模高等学校を対象としたアンケート調査の結果から、進学先として選択されない理由として、学校の状況や取組が分からないとする回答が全体の44%を占めていたこと等踏まえたものであり、4月4日の始業式、入学式から2か月間では、計43回の新着情報が紹介されるなど、高校の様子が分かりやすく、速やかに伝えることに努められている。5月に着任した地域コーディネーターも、それら広報業務への主体的な役割を果たしているが、教員でも高校生でもない立場や、協力隊として他地域から着任した感性や視点を存分に生かし、池田高校、池田町の魅力を一つ一つ発見していく日々を池田町内外の中学生やその保護者へも分かりやすく伝えてもらうことにより、生徒確保に向けた役割も期待している。
地域おこし協力隊としての地域コーディネーターはもう1名の任用に向け募集中で、同じく外部人材制度を活用し、企業から派遣を受ける方法により、さらに1名の地域コーディネーターも募集中である。質問の高校魅力化推進地域コーディネーターに町として期待する具体的な取組としては、地域おこし協力隊の地域コーディネーターには、学校と地域をつなげ、池田高校の魅力化や情報発信を、企業派遣人材の地域コーディネーターには、それら高校魅力化をさらに進めるための仕組みづくりをそれぞれ想定しており、複数人を配置することにより広報活動の強化にもつながると考えている。池田高校では、小人数ながら総合学科の特色を生かした学校活動に取り組み、町内外の多くの企業や地域の方々の協力を得ながら、探究活動や国際理解教育など特色ある事業活動が行われている。池田高校の魅力を積極的に広報、情報発信することが、地域と学校がつながること、ひいては高校の魅力化にもつながるものと考え、地域コーディネーターにはSNSソーシャルネットワークサービスなどの活用も含め、積極的かつ効果的な情報発信、池田高校の魅力発信に力を発揮されることを期待するところである。地域活性化はもとより、地域教育環境の維持確保の観点からも、地元高等学校の役割、大変重要であり、充実した学校生活と、高校存続に向けた支援を続ける必要がある。町としましても、適切なコーディネーター、人材、人員体制の確保や、池田高校及び北海道池田高等学校教育振興会などとも連携した効果的な広報活動の実施に取り組むことにより、高校魅力化への支援に努める。
再質問(片山) 広報について、SNSの活用も含めた積極的かつ効果的な情報発信等あったが、池田高校の情報にアクセスしようとしなければアクセスはない。実際にはパンフレットとかお便りとか通信のような直接渡して読んでもらえるものも、まだまだ効果的なものかと考える。昨年は予算的な問題もあってこの点はとても苦労していたと思うが、今年度は、こういった積極的な配布等は考えられているか。
再答弁(町長) 現時点ではホームページを中心とした情報発信、今後加えてセールスという話をしたところであるが、前年度までも含め町内や近郊の町の中学生に、進学を期待するところに対しては、そういった紙媒体での広報活動も当然してきている。それをしっかりと継続する中で広報手段を用いて、さらに広げていこうということで指摘のところは当然に、まずはベースになる広報活動だと認識して町として、また北海道池田高等学校教育振興会の活動としてもスムーズに進められるよう、支援をしてまいりたい。
6.将来的な人材確保の取組について
質問(片山) 3月の予算審査特別委員会で、各公園維持管理業務委託料について質疑を行ったが、その際に予算増額の理由は、人手不足が要因であった。人口減や、働き方の変化に伴って、人手不足は一層加速していく状況である。今後行政サービスを維持していくためには、新たな人材の確保とともに、現在働いてくださっている職員の方々がやめてしまう、流出してしまうということも防ぐ必要があると考える。これらの対策は。
答弁(町長) 住民サービスの土台とも言える自治体職員を取り巻く課題として、近年は本町のみならず、全国的にも公務員離れにより、人材担い手不足による行政サービスの低下が懸念されていると言われている。指摘の行政サービスを維持していくための手法としての、新たな人材の確保について、一般職員の採用に当たっては、十勝町村会による合同職員採用試験のほか、中途退職者への対応として、独自に採用試験を行っている。特に近年では、新規採用のみならず、民間企業等で培ったスキルや経験町、一般行政事務や、専門職として生かしてもらうために、社会人枠としての採用にも踏み切り、即戦力として行政サービスの向上につなげている。
近隣の自治体では、社会人枠のほかにも国家公務員や自治体職員として、マネジメント経験を持つ職員の採を実施している例もあり、本町における少子高齢化を初めとした様々な行政課題に対応するため、年齢層を考慮しながら専門分野キャリアを積んだ社会人としての経験値を生かせる人材の確保に向けて、職員採用の在り方を今以上に検討していく必要があると考えている。
また、令和2年度に新制度として創設された会計年度任用職員については、任用形態や処遇面でも適切な制度設計として運用を図ってきているが、高齢化や自己都合などの理由で任期が終了した場合、新しい任用職員の申込みに至らず、採用や人員確保では一般職員以上に検討が必要な課題も多くある。特に労務作業や一部の業種における専門職の人材が確保出来ない状況もあり、予算審査特別委員会で答弁した委託料の増大のほか、将来的に業務の継続が不安視される業種もあることは否定出来ないところである。業務上通年雇用ではない職種が原因であったり、専門性の職場における後継者の育成に至らない課題など、その要因を把握しても解決出来ない諸課題に対しては、今後も、他の自治体の制度運用のほか、処遇面の改善なども検討しながら、必要な人員の確保に努める。
一方、多くの自治体において、年齢を問わず中途退職者が増加傾向にある実態が見受けられる。もちろん退職理由は個々あるが、自治体職員として働き続けるための職場環境づくりを組織として高めていかなければならない。そのためには、職員のチャレンジ精神を養い、成長サポートしながらステップアップにつなげていく体制を強化するなど、職員の人材育成により力を入れ、組織全体の中でやりがいと誇りを持って行政の遂行に当たることができる職員の育成に努めていきたい。
7.定住促進住宅の拡充について
質問(片山) 池田町内の空き家対策、子育て世帯への支援、それから経済対策の視点から、プロポーザル事業による定住促進住宅の拡充を行うべきである。定住促進住宅の拡充による、より子育てのしやすい移住しやすいまちづくりというものが一層進められる。
答弁(町長) 住宅政策については、昨年12月の定例会議で片山議員の一般質問に対し答弁した通り、移住促進や、子育て支援と住宅施策における既存住宅ストックの有効利用、空き家対策について、一体性を持って取り組むことが重要であることから、公営住宅等長寿命化計画と、住生活基本計画の一部見直しを踏まえ、検討していくこととしている。今年の3月に見直した池田町住生活基本計画は、本町におけるこれまでの住宅施策の基本的な考え方や取組状況等を踏まえ、新たな住宅施策の目標や展開、公営住宅ストック活用の方向性等を示しているが、取組の一つとして全ての人が安心して暮らすことができる住まいづくりを掲げ、安心して子供を産み育てることのできる住まいづくり、地域づくりの推進の取組について示した。また同時に見直した池田町公営住宅等長寿命化計画では、本町における団地整備に向けては、今後の町の担い手となる子育て世帯に対するバックアップを行い、住宅困窮者にとって不安がなく安心して暮らすことのできる居住環境の整備に取り組むとし、子育て世帯や移住者の定住促進の必要性を示している。
本町における子育て世帯等の定住に向けた取組としては、定住促進住宅4棟を整備してきた。世帯向け賃貸住宅はある程度充足したと判断し昨年度で終了した、池田町民間賃貸住宅建設促進事業補助金では、民間活力を活用し、若年ファミリー層の転入定住促進を図るため、2LDK以上の間取りの賃貸住宅の建設補助を令和2年度から方向転換し、それ以降戸建住宅4戸、共同住宅4棟16戸が建設された。また今年度から子育て世帯による新築や中古住宅の取得を応援する奨励金の交付を開始している。本町でこうした取組に加え、引き続き住宅取得や住宅リフォーム等に対する奨励事業を実施することや、住情報ステーションによる空き地空き家賃貸住宅の住情報を公開することで、移住定住につながる一体的な取組を行っている。町としては、さらなる子育て世帯等の定住促進を図るため、老朽化により空き家が目立ち始めている公営住宅等を有効活用することを基本に、民間活力や議員提案のプロポーザル方式等も参考とし、池田町で安心して暮らせる住環境を整備し、定住促進を進め地域経済の活性化を図り、持続可能な地域づくりに取り組んでいきたいと考えている。
再質問(片山) 世帯向け住宅、賃貸住宅がある程度充足したという点については、十分充足されていると考える。空き家の状況になっている建物の活用をする中であれば、まだ進められると考える。例として清水町では、総工費550万円ほどでプロポーザル方式で事業者を選定し、町内の事業者が内装の全面改装を行った建物、専用住宅の改修を行い、それが多くの方々に使われているという、事例がある。定住促進住宅の拡充を行うことで、子育て世帯の戸数が増えれば、それだけ将来そこから池田町に定住してくれる。その子どもたちがもしかしたら戻ってきて定住してくれるかもしれない。住んでる人が池田町内に家を建てて、定住してくれるかもしれないといった期待が大きくなる。池田町はまだ、移住定住については、大変外から見たら魅力のある町である。先日、建設業界の方々との意見交換会では、町をよく知っている町内事業者の方々が、この建物の改修の提案も十分可能であるといった力強い返答もあった。定住促進住宅の今使っていない建物の改修による、定住促進住宅の拡充というものは積極的に進めてよい。
再答弁(町長) まず住宅施策について、本町が取り組む少子化、人口減少対策としては極めて重要な、施策であるのが住宅政策であり、当然に将来的に向かっての定住効果といったところも大きく期待をできるものと思う。その中で議員御指摘のように、町内商工事業者のほうから、改修などの提案ができるというお話であり、そこについては町としましても、民間活力といったところで非常に期待も出ているところである。単に改修するということではなくて、そもそも設計や施工にとどまらず、場合によってはその管理運営とか、いろんな意味で民間活力が投入されていくことも、また住宅政策の中でも重要であると私自身は思っている。そもそも、新築のところについては、昨年まで行ってた民間賃貸住宅の促進で、さらにそれよりも定住効果が高いだろうということで、持家であるところへの子育て世代に対する支援の強化というところを進めているが、一方でそこまでの住宅環境を求められない、そういった住宅ストックとしてまだ別な形で必要性を認識される方々も当然にいらっしゃると思うし、そこは既存の池田町の資源をさらに有効に活用するという意味合いで、住宅政策の中でも空き家等の活用についても併せて、答弁したようにその中では民間活力また議員指摘、提案のプロポーザル方式等も検討しながら進めてまいりたい。