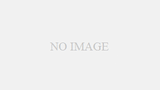一般質問
9月8日に定例会議2日目は一般質問が行われました。4名13点の質問があり、片山は下記の通りです。一般質問の記録映像を本記事の下部でご視聴いただけます。池田町議会ウェブサイトでも過去の中継のご視聴が可能です。
【質問内容】(概要)
【質問1.上水道の維持管理について】
(質問)
下記の2点を伺う。
1)今後水道網を維持していけるか、運搬送水を採用しうるか所見を伺う。
2)先端技術等の導入により町が主体的に上水道維持を進めていくことについて所見を伺う。
(答弁町長)
1)今後は大規模な管路拡大は想定しておらず、現段階においては計画的な配水管の更新を行うなど、現状の水道網を維持していくことを基本としている。運搬送水については、現段階では今後の末端部分での需要状況等に不透明な部分が多いことから、検討していないものの、今後の動向によっては給水方法の選択肢の一つとしてとらえていく必要がある。
2)AI管路劣化診断技術や人工衛星漏水検知などの活用については、大変有益な技術だと認識している。最新技術の情報収集や新しい発想・工法等を注視しながら検討していくことが効率的で健全な施設維持につながるものと考えている。
(再質問)
毎年2%の継続的な更新を行えば50年ですべての管路更新が可能で、次のサイクルに入ることができる。費用が毎年上がったり下がったりするのは財政上のリスクになりうるので、毎年安定的、継続的に費用をかける長期計画を作って実行できないか。
(町長答弁)
現在の経営戦略、計画については議員が想定するよりも短いスパン(令和20年まで)だが、そこにAI技術を導入しながら、一方では長期的なスパンによっての計画を策定すべきと考えている。
【質問2.総合体育館の維持管理について】
(質問)
総合体育館について、多目的室や柔道場、剣道場はその機能を十分に維持できていない。夏は暑く湿度が高すぎるため熱中症の危険と隣り合わせである。本来の機能が発揮できる程度に、多目的室や柔道場にはエアコンや空調設備の整備が必要である。剣道場は部屋の劣化が進行し、構造体にも影響するのではないか。これら多目的室や柔道場、剣道場の機能維持に対する所見を伺う。
(教育長答弁)
教育委員会としては総合体育館の機能を適切に保全し維持管理していくことは重要であるとの認識の下、これまで施設設備の改修や補修、スポーツ機器の導入等に取り組んでいる。多目的室は気温上昇による体調への影響も懸念されることから、速やかな設置は難しいものの大型扇風機を2台増設する対策を講じたところである。柔道場についてもエアコン設置を望む声があることから、今後剣道場の機能維持も含め、町長部局における公共施設全般のあり方を検討する中で、総合体育館の機能維持の視点をもち、良好な環境整備について協議を進めたいと考えている。
(再質問)
今年度は夏も終わりを迎え、今すぐに設置する必要は無いと思うが、来年もまた異常な暑さの夏が来るかもしれない。エアコンは費用がかかるものの移設することも可能である。子どものかかわりがある場所であり、暑さで死んでしまってからでは遅い。子どもを守るのは我々大人の責務である。今後検討するとのことだが、どれくらいの間検討するか伺います。
(教育長答弁)
教育委員会としては、子どもたちの安全安心な環境整備を大前提に、公共施設全般に渡る町長部局との検討の中で検討を進める。限られた財政の中で何を優先するかは町全体のことであり、令和6年度当初予算においてどの程度のことができるのか町長部局と検討したい。
【質問3.通学路の危険個所の整備、安全対策について】
(質問)
池田小学校PTAで作成されている通学路安全確認マップがあり、多数の危険個所が記載されている。例えば役場前の踏切周辺は大変危険な状況である。踏切の西側は道道なのですぐには対処できないかもしれないが、東側は町道なので啓発看板を設置するなど安全対策を行うべきである。その他多数の危険個所があり、少しずつ解消しても解決は難しいのではないかと考える。そこで、池田町の単独事業としてでも町全体の危険個所を包括的に解消する事業はできないか。
(町長答弁)
議員指摘の交差点は鉄道や交差点を含んだ道路形状からハード的な解決は難しいと考え、啓発看板については池田警察署やJR等と協議し、交通安全の啓発として早急に歩道等に注意喚起の看板を設置するなどの方法を検討する。
町全体の危険個所を包括的に解消する整備安全対策については、学校からの要望は引き続き池田町通学路安全推進会議で協議の上対策を検討し、必要に応じて国や道への関係機関に対しても改善要望を行っていく考えである。
【質問4.災害融資居ついて】
(質問)
現在燃料費をはじめ物価上昇が続き、事業者の経営環境は6月よりも悪化している。コロナに関わる災害融資が借換えによる延長等ができる状態にすべきである。6月定例会で一般質問した災害融資の出口戦略について進捗状況と今後の見通しを伺う。
(町長答弁)
資金需要把握のため関係機関等から聞き取りなどを実施し、町内の資金需要が大きいとはいえない状況と認識している。昨今の目まぐるしく変わる情勢の下、今後も需要を見極めながら、運転資金の融資枠の拡大についても引き続き検討していきたいと考えている。
(再質問)
消費者物価の総合指数は前年同月比7月時点で3.3%の上昇。企業物価指数は同4.3%の状況と、企業のコストを価格に反映できない状況である。また冬が来ると新たに多額の燃料費が発生する。検討状況について、いつまで検討されるお考えなのか伺う。
(町長答弁)
町内事業者を守るという観点で、そこに対して常に関係機関からの状況把握をして、町内事業者の状況の把握をしながら進めている。現時点では大きく災害融資に関する更新であるとか、運転資金枠の拡大等について、需要が非常に高まっていて早急に対応する状況にないと判断している。今後状況によっては必要にあれば年度中にあっても検討していきたい。現時点では次年度に向けた状況を見極めながら状況を検討している。
【質問5.ペーパーレス化の推進について】
(質問)
役場内では標準の用紙で昨年度192万枚以上が使われた。資料作成には用紙代に加え人件費や時間、ミス時の再印刷や訂正、謝罪等の費用もかかる。ペーパーレス化でこれらが一気に解消され、行政サービスの充実向上にもつながる。先行事例は多数あり池田町も進められないか。
(町長答弁)
一部職員は令和5年度の当初予算編成から完全ペーパーレス化しており、会議も紙の使用を最小限にするなどしている。6年度は原則職員の業務パソコンは持ち運べるものに更新し、ペーパーレスの業務環境を整備していく予定である。業務等により紙を併用する。
【質問6.キャッシュレス決済やオンライン行政サービスの導入について】
(質問)
池田町でキャッシュレス決済やオンライン行政サービスをより積極的に展開し、町民の利便性向上を進めていかないか。
(町長答弁)
オンライン行政サービスについては、防犯灯の故障を通報する申請フォームからの通報や、町有施設の貸館申請は可能になっている。指定管理の総合体育館はオンラインの利用申請に対応し、図書館は図書の予約も可能である。キャッシュレス決済は、本町では令和4年度から町道民税など主要4税と水道使用量についてコンビニでの支払いが可能になったほか、今年度からは固定資産税と軽自動車税について各種QRコード決済を導入するなど、キャッシュレス化の時代に対応した行政サービスを行ってきている。住民票や印鑑証明書、課税証明書の交付はデジタル田園都市国家構想交付金を活用しマイナンバーカードを所有している方は役場窓口だけでなく、全国のコンビニで交付申請ができるよう今年度中のシステム稼働を目指している。
窓口でのキャッシュレス決済やオンラインによる証明書請求については課題も多く、また今年度末から開始されるコンビニ交付サービスにより窓口と郵送での証明書交付件数が削減されるため、それらの効果を確認したうえで導入の可否について検討していく。
(再質問)
様々な取組がされているが、どこに何があるのか分かりにくいので、ホームページ上に何に対応しているのかがわかるようにするのはいかがか。また、郵送による課税証明書の申請には返信用封筒と郵便小為替の用意が必要であるが、マイナンバーカードの所有の有無にかかわらずもう少し便利な申請しやすい方法も選べるようにできないか。
(町長答弁)
一括して把握できる状況ではないので、しっかり利用できる周知や住民の皆様への使用啓発も必要であると認識しているので進めていこうと考えている。各種証明書の発行について、マイナンバーカードの所有に限定されているということについて、所有していない人に向けては課題認識として持ちながら今後の動向を注視しながら検討していく必要があると考えている。
【質問7.森林施策と森林環境譲与税の活用について】
(質問)
1)今年度の森林施策は具体的に何を目標として、何ができれば良いと考えているか。
2)町内事業者との連携や支援について現状と、今後の考えを伺う。
3)森林環境譲与税の活用方法として池田町にとって最適な使い方はどこにあると考えているか。
4)来年度以降について森林環境譲与税を何に活用していこうと考えているか。
(町長答弁)
1)本年度事業については、「位置情報共有システム普及に係る事業」「近自然森づくりワークショップ」「森の輪プロジェクトの推進」「民有林管理推進事業」「豊かな森づくり推進事業」「林道基盤整備事業」「炭焼き体験の指導や木育の実施」「林道の路肩の草刈り」「小規模維持管理工事」を実施している。町有林においては公有林の有する公益的機能の維持増進、森林及び森林資源の育成を図り、製炭用原木の安定供給に向けた町有林での天然林間伐、人口造林事業を実施している。このほか農村生活の未来に夢と希望を与え、営農意欲の効用を図り、農家経営の安泰を目的とした農業後継者結婚造林等の分収事業にも取り組んでいる。
森林の有する公益的機能を維持しつつ、資源の計画的な保続を図ることを目標とし、伐採跡地への確実な造林と伐採率を押さえた間伐の実施など適切な森林整備により、人工林資源の適切な管理体制による持続可能な森林づくりを目指すものである。
2)町としては事業者の皆さんと連携しながら、今後もさらなる協働を実施していきたい。事業者支援としては、林業グループの活動を支援する補助金、弱度間伐を実施する民有林管理推進事業補助金、林業機械や安全装備導入を促進する林業基盤整備事業補助金、豊かな森づくり推進事業補助金を予算計上し実施している。
3)今後は町内の森林資源の把握、既存の作業道など現時点では把握できていない林内路網を詳細に把握するための航空レーザー計測事業を実施する計画があり、町内全域を計測するためには相当額の基金を充当する必要があると見込んでいる。
森林整備計画には公益的機能別施業森林が規定されている。必ずしも経済的な森林機能ではないが、安全に豊かに生活するために必要な機能である。森林環境譲与税の充当が見込めるものについては、これを財源として、これ以外についても計画推進のため各種補助金、有利な財源を確保しながら適切に進めていく。
4)森林環境譲与税は来年度以降もこれまで継続してきた施策に加え、航空レーザー計測実施のための検討も進めながら、森林に多面的な新たな価値を見出し、未来につなげるような林務行政を実施するため、森林環境譲与税を財源とした各種事業を計画し推進することで有効に活用していきたい。
(再質問)
多くの事業が進められておりものすごい作業料だと思うが、人員体制は大丈夫か。外からは見えづらいが産業振興の点からも重要な部分なので町民に向けた情報発信も積極的に行ってほしい。全体として森林の保全整備が中心の印象だが、活用する面については何か町として進める意向はないか。豊かな森林資源があるので、町内で育て加工し、エネルギーにして、また植えて、、といったサイクルも作れるのではないかと考える。
(町長答弁)
林務に対する人的なこともあり、一部停滞をしているものもある。いずれも継続的な事業が中心であるので、継続すべきものは継続し、見直しを図る必要のあるものは見直す。残り半分少々となったが、個年度もしっかり取り組みたいと考える。新たな取組で今年度始まっている林道基盤整備事業で、全額を森林環境譲与税を充当しているが、町内事業者との連携を図るうえで、機器等の経費を補助する制度を始めているので、計画に基づいて進められるようにしていく。
森林の利用については、木質バイオマスの利用も今後においては不可欠であると思っている。これまで町内で協議会も立ち上げ、チップバイオマスの検討も進めてきたが様々な課題に直面して検討以上に進まなかったという経過もある。様々なコスト面の課題については森林環境譲与税もあるので、活用しながら進める方策であろうと思う。現在は林業だけで考えることではなく、本町は地域再生可能エネルギー導入計画策定を進めているところである。太陽光や木質バイオマスが十分に活用を想定されるところだが、初期導入などの環境整備についてはこういった財源を活用しながら進めることを実施とまでは言い切れないが検討する必要があると考えている。
【質問8.町有林貸付事業について】
(質問)
6月定例会で一般質問した町有林貸付事業の整備状況はどうなっているか。6月時点では一時的な休止という認識でいた。継続的事業、町有林の活用、歳入に係る事業、新しいブランドが生まれた実績を持つ事業という各点からも大変良い取組であると考える。課題や問題点の改善を図り事業が再開するのか、今後本事業をどのようにすると考えているのか。
(町長答弁)
現在契約内容の見直しなどを検討しているところだが、現時点では貸付事業の再開には至っていない。本年度における事務事業の執行については再開に向けて準備を進めていて準備が整い次第酵母を開始していく考えである。町有林の適正な管理を進め、一方で森林から様々な恩恵が受けられ、健全な森を維持していくため、林業のすそ野を広げる本貸付事業を進めていく。
(再質問)
どのような仕組みで再開するかにもよるが、事業者が様々な取組を行えるようにすることで、新たな森林の活用方策や産業の六次化への道筋なども見えてくるかもしれない。前年度までの契約は縛りが大きいものであったと思っているが、新たに再開するときに同様なものになるのか、大きく変わって自由度が高くなるのか。どのような方向で再開したいと考えているか。
(町長答弁)
町有林の貸付事業は林業のすそ野を広げるという点で重要だと認識している。昨年までの賃貸借の契約では何ができて何ができないのかが明確ではなく、自由度をもって新たなチャレンジができるという契約にはなっていない。自由度を認めるところは認め、管理していただくところはしっかりしていただくという意味での見直しを行っており、そこが再開に至るまでの状況に契約の見直し作業が至っていない。これから季節的には森林空間を活用するところでは難しいという考えもあるが、冬の方が管理しやすい面もあるので、時期や季節にとらわれず事業が再開できるように新たな取組、自由度が持てる、そういう取組につながるような契約内容の見直しを含めて進めていきたい。
【質問9.孤独死対策について】
(質問)
池田町の孤独死対策の現状と今後の対策について考えを伺う。
(町長答弁)
議員指摘の通り、一人暮らしの家庭で町に対し相談があり死亡を発見したケースが今年に入り数件あったが、孤独死の定義が明確でないこともあり、町全体の正確な発生件数は把握できていない。孤独死は年齢や障害、持病の有無にかかわらず主にひとり暮らしの方であればどなたでも起こりうるものであり、地域における予防の取組が重要になっている。
そこで本町では、特にリスクが高い高齢者を中心に緊急通報機器42件を無償貸与し、配食サービスでは95件が登録し協力店による見守りを行っている。このほか民生委員をはじめ地域住民による見守りや新聞・宅配業者等の民間事業者3社と協定を結ぶなど、異変等の早期発見について協力をお願いしているところである。また、高齢者が孤立せず社会とかかわっていくことも重要であり、介護予防事業等の参加も呼び掛けていく。
今後も希薄化した地域の人間関係を結びなおす機会を拡充し、社会から孤立した状況を防ぐ取組を地域全体で進めるとともに、ICT機器等の活用も検討しながら日常的な孤立状態の解消を図り、孤独死を迎えずに済む関係づくりや環境づくりに取り組んでいく。
(再質問)
高齢者だけでなく若い人への対応は。配食サービスの周知を対象者だけでなく町民全体にしては。
(町長答弁)
年齢に関わらず地域のコミュニティ、若い方も色々な目標や考えがある中で人と人とのつながりを強く意識しない時もあろうかと思う。そこに関しても池田町として地域のつながり、決して大きな自治体ではないので進めやすい環境であると思う。多世代の方が交流できる機会も増やしながら進めていきたい。
配食サービスを広く周知をということだが、今は対象者に伝えているが、改めて池田町としてその取り組みをしていることは対象者だけでなく町全体の人が認知できることで地域のお声がけをされるということもあるので、そういった周知活動もしていきたい。
提出した一般質問の通告書です。調査継続中のものや情報収集や事実確認が間に合っていないものがあるため、確実ではないものについては次回以降行うか、再質問等を行う対応になります。
●池田高校の支援
●通学路整備
特に役場庁舎建物前の踏切がある道路について、警察の交通取締りにより頻繁に(ほぼ毎日?)検挙されている状況にあると感じています。(実数は調査します。)これだけ頻繁に検挙されているということは、もはやドライバーというよりは道路の方に問題があるのではないでしょうか。ここは小中学生が多く通る通学路であり、交通指導員の方々が見守りを行っていますが、2~3年前には指導員の方がはねられるという状況です。この道路を含めて、池田町学校で作成されている通学路安全確認マップでは〇箇所にも及ぶ危険な個所、注意を要する箇所があげられています。庁舎前の道路は道路標示も良く見えない状況であり特に危険な状況であり、改善の要する箇所の改善や修繕が必要であると考えています。いかがでしょうか。
●小中学校教科指導・生徒指導体制
いじめ、不登校の状況について。
●道路危険個所、修繕、街灯不点灯などの町民通報システム+防災面での通報システムの導入+住民票など行政文書のオンライン申請システム
帯広市や他の町村でも導入されている画像で道路の修繕個所や該当不点灯個所の町民通報システムについて池田町でも導入できないでしょうか。帯広市で導入されているシステムはLINEが使われていますが、画像と位置情報を同時に送信が可能で、緊急時は電話での通報を選択することもできます。同じシステムで災害時は防災面での通報システムとしても使えるようにすることで、災害発生時に被害箇所や被害状況の情報収集が効率的に行うことができるようになります。情報が入らない場合は壊滅状態ということも考えられるため、支援や救援の優先順位も設定しやすくなります。
●災害融資
進捗状況はいかがでしょうか。
●森林環境譲与税・森づくり
森林環境譲与税が基金として積みあがっています。過去に行われた所管事務調査では事業の進め方に苦慮している状況であるのは分かりますが、「予算を使うために何をするのか」と、視点が短期的なものになってはいないでしょうか。将来的にどのような森を作るのかという展望をもって、そのために何が必要か、何が不足しているか、それを解決する手段として森林環境譲与税や基金、国や北海道の補助金を活用するという形で長期的な視点を持った事業計画を立てられないでしょうか。
近年池田町では広葉樹の森に関わり様々な取組が行われてきたことを承知しています。池田小学校での森林体験学習や池田高等学校での商品開発授業、白樺製品ではオリジナルブランドの「ホワイトバーチ×イケダ」が誕生しました。
6月の定例会議で継続的事業の継続について一般質問のきっかけとなった「町有林貸付事業の休止による事業者の契約継続断念」は、町として森づくりの展望を持っていれば起こらなかったことではないかと思います。池田町は豊かな森林を有しており、町の財産であると考えています。この森の今後の姿として、私はこれまでの池田町の取組や現在行われていることから、「池田町は動植物が豊かな森に囲まれている地域性にある。動物と人との境界線(緩衝地)として、人の手により整備された森づくりを行う。鹿や熊などの動物が人の住む地域に出てきて人に害を与えることを防いだり水災害を防いだりする公益性を確保する。整備の過程で収益が得られる収益性も確保する。無理に広げる必要は無い。鹿は狩って、地元で加工することもできる。」といった森づくりもできるのではないかと考えています。子供から大人まで「自然と触れ合える場」や「学びの場」としての森、仕事を退職してからは時間や売上に縛られることなく森を整備し、材を生産し、次の時代につないでいくという「生きがいの場」としての森といった森づくりもできるのではないかと考えています。池田町はこれからどのような森づくりを進めていくのでしょうか、いきたいのでしょうか。今後の展望をお尋ねします。
●町有林貸付事業
町有林貸付事業について、契約がある予定だった事業者が契約継続を断念したため当初予定での実行はされていないことは理解していますが、その後整備の状況はどうなっているでしょうか。歳入で予算建てされているので、歳入目標に向かって事業を進めていただきたいと思っています。新しいブランドが生まれた実績もある事業なので良い事業なのだと思います。年度当初の課題や問題点の改善を図った形での事業は行われているでしょうか。
●孤独死対策
ここ数年、私の周辺でも一人で亡くなり、しばらくの時間を置いてから発見されるという孤独死の話を聞く機会が複数ありました。町全体では相当数にのぼるのではないかと思います。人間であるから死は避けることのできないことですが、誰にも気づかれず、相当の日数が経ってから発見される最後というのは大変痛ましいです。孤独死は高齢者に限らず、障害や持病をお持ちの方や生活に困窮されている方にも起こりうることです。今後ますます高齢化が進む池田町は、高齢者の一人暮らしの方が増加していきます。十勝管内でも平均所得が低めであることからも、困窮する方の増加も考えられます。池田町の孤独死対策の現状と今後の対策について考えを伺います。
●業務のペーパーレス化
●町が保有する施設の空調(冷房)の整備状況について
●困窮対策
●子育て支援
●幼稚園・保育園
●事業環境関連
国道242号線→道道73号線→道道237号線(大通)沿線整備について
●ワイン事業、ワイン城会計について
売上高をもっと。東京事業所の必要性。