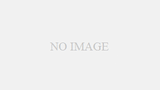6月22日に一般質問を行いました。全5問10項目、再質問4項目でした。概要は下記の通りです。双方の内容は概要です。正確でない部分は議事録を確認後に訂正と修正をするかもしれません
【質問1:池田高校支援】
(1)質問:1年生向け助成金400万円の未執行分を高校存続の後押し資金にできないか。
→答弁(町長):未執行分を活用するのではなく、必要な活動にはしっかり補正予算や当初予算で議会に示しながら取り組んでいきたい。
→答弁(町長):これまでの取組を継続しつつさらに充実した広報活動に取り組む。支援の一環として広報物は公区配付で町内全戸に配付し、多くの方に池田高校の魅力を知ってもらえるよう取り組んでいく。
(3)質問:地域コーディネーターの配置など外部人材の活用により先生方の負担軽減や授業の質の向上を。
→答弁(町長):配置の必要性や実施体制などを協議していきたい
→再質問:池田高校が拒否するということはないと推察する。高校が拒否しない限り配置すると受け止めて良いか。
→答弁(町長):配置と実施体制の協議を進めていく。
(4)質問:総合学科の特徴に合う形で生徒のスキルアップに直接つながる支援になるよう補助金の活用を。
→答弁(町長):(3)のコーディネーターや講師謝礼などを含め、どのような支援が必要か継続的に協議を重ねているので、考えがまとまった段階で議会に示す。
(5)質問:利別地区と池田高校を結ぶ通学バスの運行を。
→答弁(町長):通学バスではなく、コミュニティバスを10月からのダイヤ改正に合わせて朝の1便について池田高校まで路線を伸ばす見直しを行うため、6月下旬予定の池田町地域公共交通会議に諮る。
【質問2:継続的事業の担保】
(1)急な方針変更により継続的事業が休止になり、契約の継続を断念した事業者がおられます。こんなことが繰り返されては池田町で事業を行おうとする人がいなくなることが危惧される。(1)議決された事業は年度当初から正しく遂行すること。(2)安易に事業をやめることなく、事業の継続性を維持すること。
→答弁(町長):町としては契約内容の調整後事業の継続意思があったが、説明の際に丁寧さが不足し、互いの認識に齟齬が生まれたと思われ、契約締結に至らなかった。事業の見直しが必要となることも否定できないので、その場合については様々な影響を考慮し可能な限り、早期検討と影響を受ける事業者への丁寧な説明を行い理解していただき進めていきたい。
→再質問:3月の議決を受けて4月開始する事業で4月に休止を通知するとはあまりにも遅すぎる。せめて3カ月前には通知を。他にも類似の(休止中、休止予定)の事業はあるのか。
→答弁(町長):今回は非常にレアなケースであり、他にはあまりないものと認識している。原則としては予算計上前に見直すべきであると認識している。
【質問3:防災情報や避難行動など災害対策について】
(1)質問:災害時にペットと一緒に避難する避難者の受け入れ態勢は。
→答弁(町長):本町の各避難所の屋外にはペットの係留ができる場所は事前に確保できるが、屋内では十分な確保が難しい。自動車を所有している場合は車中避難をお願いすることも必要と考える。避難体制については、飼い主としての責務や町の支援体制の確立を踏まえたうえで、住民羞恥と共に受け入れ態勢については他の自治体の取り組み状況を参考に検討していく。
→答弁(町長):国土交通省のハザードマップポータルサイトを活用して、町公式サイトのトップページにある「もしものときは」に掲載されている避難所の一覧及びハザードマップの各ページに、ポータルサイトの情報を組み込んで表示するよう修正した。町単独での整備には構築・運用に一定の費用が発生するので既存のシステムを活用していく。今後も防災情報をわかりやすく発信できるよう努める。
【質問4:災害貸付資金の出口戦略について】
池田町中小企業融資条例で災害貸付資金の融資が行われている。コロナの影響に続き物価高が進行し事業者の経営環境は厳しさを増す一方であり、この状況下において災害貸付資金の当初予定での返済継続は負担が大きすぎる。融資期間の延長や、別枠で運転資金などへの円滑な移行を行うこと、保証協会の保証料は一部補助するなど、事業者に寄り添った形での災害貸付資金の出口戦略を描き、町として最後まで事業者を支援するという姿勢を示せないか。
→答弁(町長):償還期間の変更や運転資金の別枠を設けることで事業継続の観点から一定程度の効果を見込めるとは考えるが、ほぼすべての融資案件について償還が始まっており、場合によっては債務者区分の低下など事業者のデメリットが発生する恐れがあるため、現在のところ需要は未知数である。今後も需要を見極めながら施策を検討していきたい。
→再質問:資金繰りが厳しいときには「追加融資」「リスケジュール」「借換」の対処法があるが、借換えについてはデメリットが起こらず、追加運転資金の借入も可能であると思う。全国的に多くの中小企業がコロナ融資を受け、現在は元金返済開始のピークを迎えている。国は借換補償制度を開始しており、借換えによる資金繰りの安定化が可能になっている。町についても事業者の資金繰りの安定化を可能にする手段の用意を。需要が少なくても最後まで支援するという姿勢はあるか。
→答弁(町長):検討していく。
【質問5:空き家対策について】
国の「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正法」を受けて、池田町は今後の空家対策についてどのように考えるか。
→答弁(町長):法律に従って手続きを進めていきたいと考えている。特定空家等を増加させないため、引き続き法令や各種補助制度の広報、周知等に努め空き家などの解消を図っていく。
→再質問:早期の助言や指導はもちろん、行政代執行についても積極的に行っていく必要があると考える。積極的に行うことについてどう考えるか。
→答弁(町長):基本姿勢としてはなるべく早く有効な手立てを講じていくことが大前提と考えている。助言、指導…と順をおったうえで、最終的には固定資産税の軽減解除や行政代執行も避けては通れないと、自治体としても検討取組申していく必要があると考えている。
議会中継の記録はこちらからご覧いただけます。↓
通告書の内容をダウンロードできるようにしました。6月12日(月)
令和5年6月議会に関連する内容を追記・修正する形で、公開可能なものについて公開します。
【一般質問で予定する内容】
池田高校の支援について(1)池田高校生に対する助成金の未使用分の扱いについて
(2)小中学生やその保護者に向けて直接、池田高校の活動内容や良さを伝える取組について
(3)池田高校のコーディネーター設置等、負担軽減策について
(4)池田高校生に対する助成金の運用方法について
(5)利別と池田高校を結ぶ通学バスの運行について防災情報や避難行動など災害時の対応について
(1)児童生徒の登下校時など、Jアラートや地震等の非常事態発生時に町内が一体として行える避難行動の対応について
(2)ペット同伴の避難について(避難行動、避難場所、ペットの対応、事前周知など)
(3)オンラインハザードマップの活用及びその周知について町有林の貸出に関わり、継続的事業の継続性を担保する取組について
ここより下の文章は上記項目について補足説明です。実際に一般質問する際のもとになる文章であり、このままの内容を議会で話すことは致しません。
池高(1)池田高校生に対する助成金の未使用分の扱いについて
池田高校生に対する助成金として10万円×80名分の予算が組まれていますが、実際の入学者は80名に満たないため予算があまり、補正予算の際に減額されている状態です。その際に、本来生徒に使われるはず立った助成金を、次の生徒の獲得に向けた資金としてPR活動等に使える予算に補正予算で組み替えて、池田高校の存続を後押しすることはできないでしょうか。池高(2)小中学生やその保護者に向けて直接、池田高校の活動内容や良さを伝える取組について
現在の池田高校は、高校入試を迎える生徒やその保護者、地域の方々にその魅力を十分に伝えられていない状態です。近隣の小学生や中学生には学校を通して毎月1回定期的に直接チラシを届けるなどして池田高校の魅力を伝えるといった、池田高校のPR活動をもっと積極的に進めていかけないでしょうか。池高(3)池田高校のコーディネーター設置等、負担軽減策について
池田高校で行われている参画の授業では、町内事業者や町民の協力があると非常に効果的な授業が展開できます。池田高校と町内事業者や町民、池田町と橋渡しを行うコーディネーターを設置することで実現できるので、コーディネーターの設置あるいは同様のことを池田町が行うことはできないでしょうか。また、池田高校の支援の在り方としては、ご家庭の負担軽減策が主となっていますが、現在実務を担当されている池田高校の先生方は多忙を極めている状態です。その負担軽減につながる支援として、コーディネーターの配置(学校-地域-池田町の三者をつなぐ人)の他に、チラシやポスター制作、ホームページ更新、学校説明、宣伝など本来業務以外の負担軽減策も実行できないでしょうか。池高(4)池田高校生に対する助成金の運用方法について
現在の池田高校の支援の在り方としては、ご家庭の負担軽減策が主となっていますが、生徒のスキルアップに直接つながる支援に重きを置く方が良いと考えます。(例えば… 地域の事業者による授業、生徒主催の行事、その支援を行う教員に対するもの….など?情報収集中です。)池高(5)利別と池田高校を結ぶ通学バスの運行について
昨年度実行されたJR池田駅→池田高校の通学バスは大変良い成果が出ていると聞き及んでいます。この通学バスについて、特に冬期間中は通学が非常に困難になり、保護者の方々の送迎の負担が大変大きくなる利別地区の生徒も対象とし、バス停留所を一か所設けて「利別地区→池田駅→池田高校」の通学バス運行もするべきであると考えます。町有林の貸出に関わり、継続的事業の継続性を担保する取組について
町有林の貸出事業に関わり、今年4月の人事異動をきっかけにして「これまで池田町が継続して行ってきた事業で」、「新年度で予算に組まれているにもかかわらず」、一方的に事業が休止された事業者がいました。結果としてこれはこれから池田町に定着し、事業を展開し、発展させようとしている事業者を追い出そうとする行為になりました。
現在も進んでいますが、これからの池田町は人口の減少に伴い、事業者数も減少していくことが予想されています。これは池田町だけでなく日本全国で進んでいることですので、町の外からわざわざ池田町に来て事業を興し、定着してくれるという方は個人、法人を問わずとても貴重な存在です。今回の件のようなことが繰り返されれば、池田町で事業を興したい、池田町に来たいという事業者がいなくなってしまうだけでなく、町内で事業を展開しようとして頑張っている事業者が外へ出ていってしまうことも考えられます。今後同じようなことが繰り返されないよう、下記の内容について実際の行動を伴う取組を行っていただきたいです。
(1)議会で審議され議決された事業は年度当初から正しく遂行すること。(特に継続的かつ相手がある事業)
(2)行われている事業は安易に停止や廃止、中止、休止するのではなく事業の継続性を担保すること(特に継続的かつ相手がある事業)
(3)申請者や利用者がいる事業は可能な限り事業者に寄り添ってその想いを実現する努力をし、継続事業については一方的な通知による停止や廃止、中止、休止を行わないこと